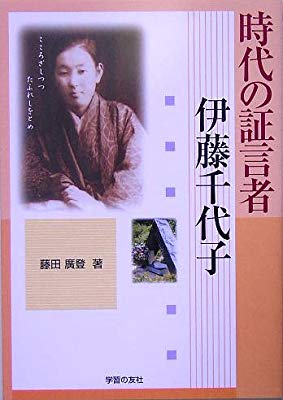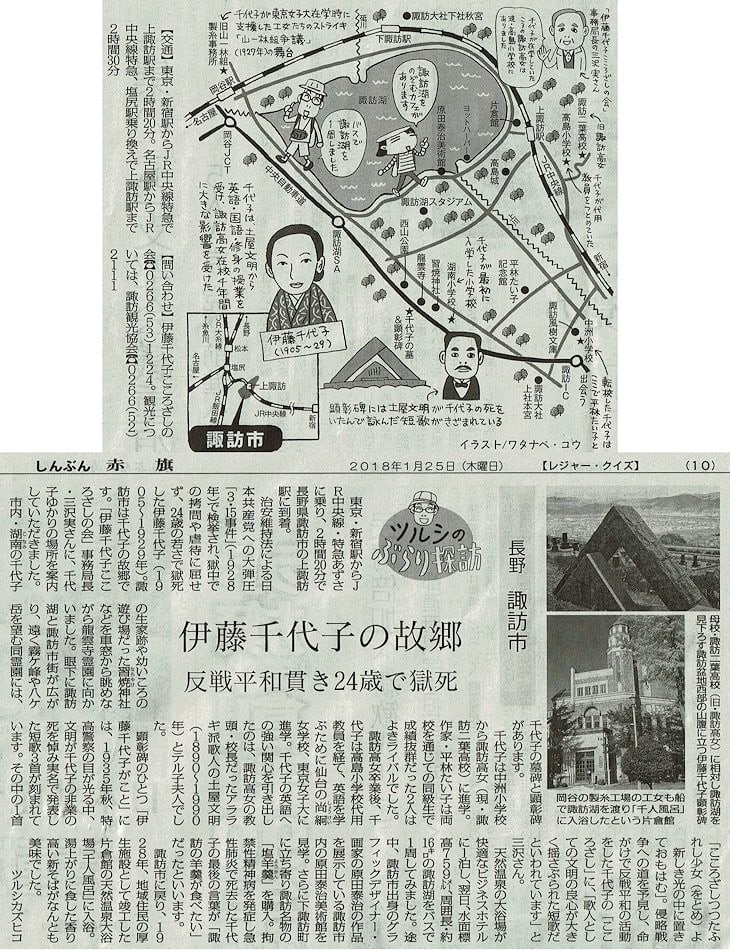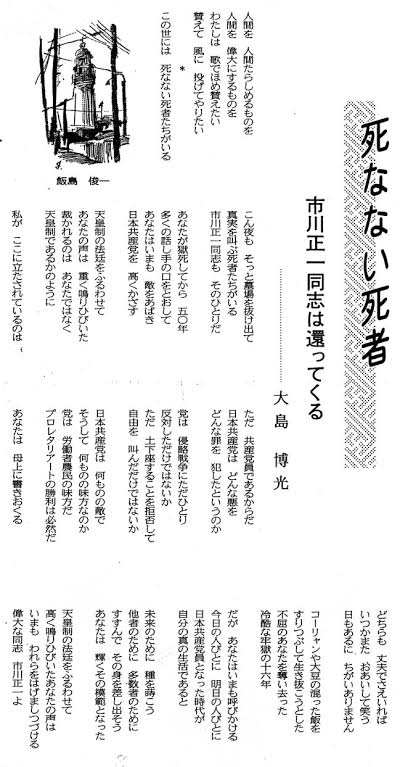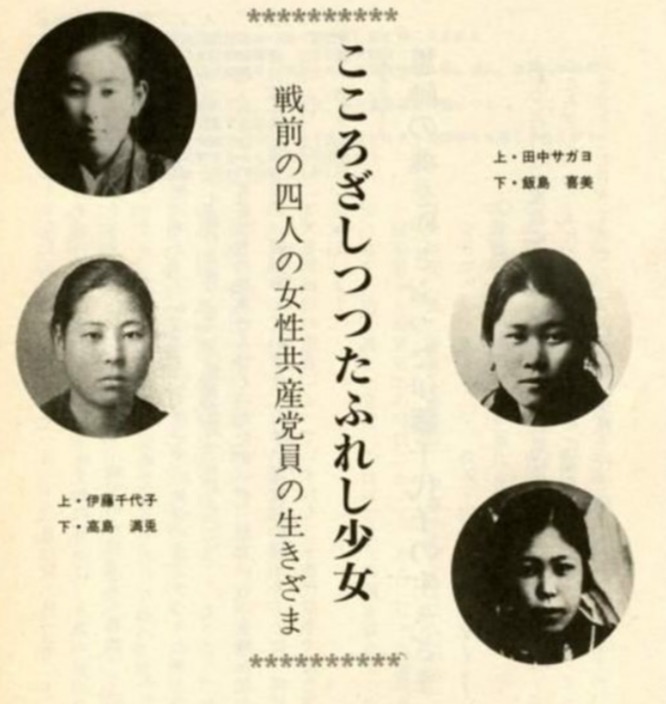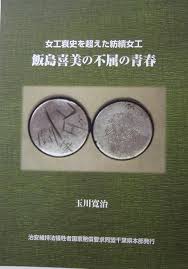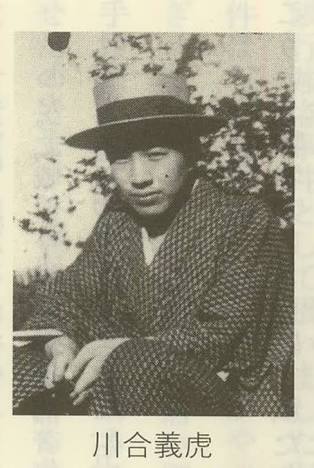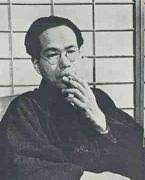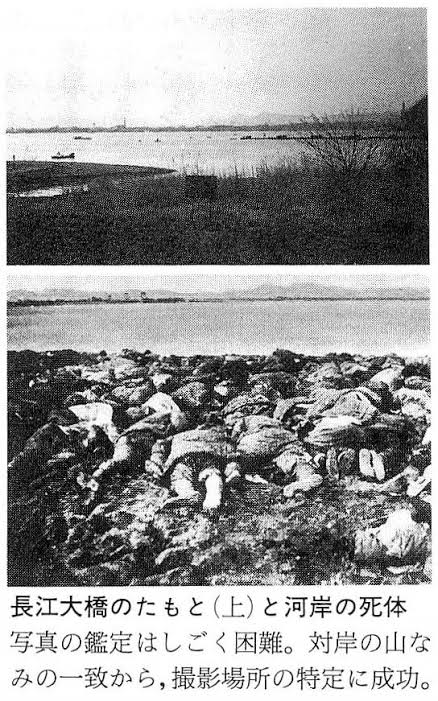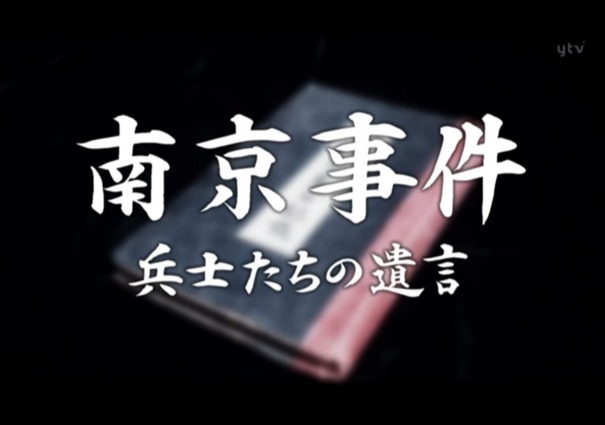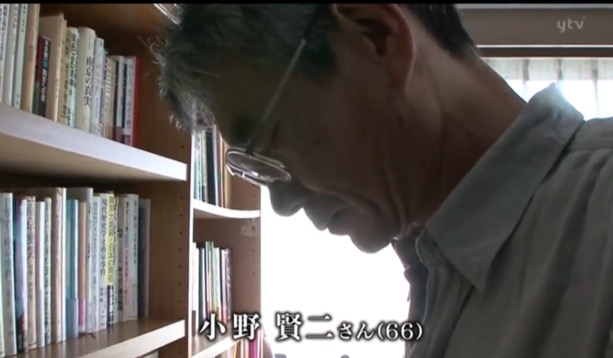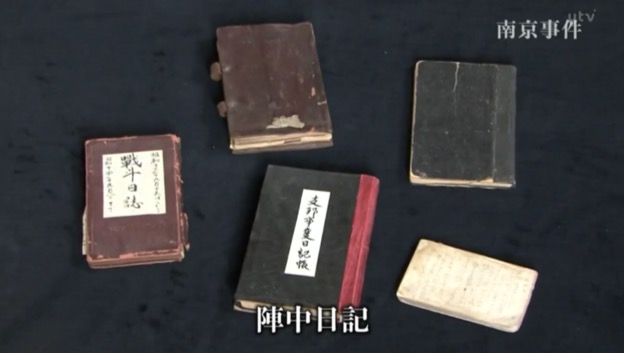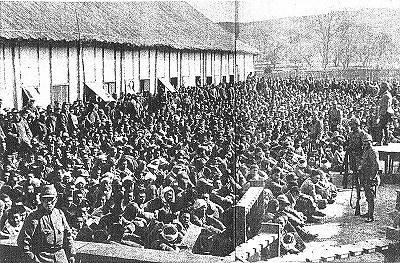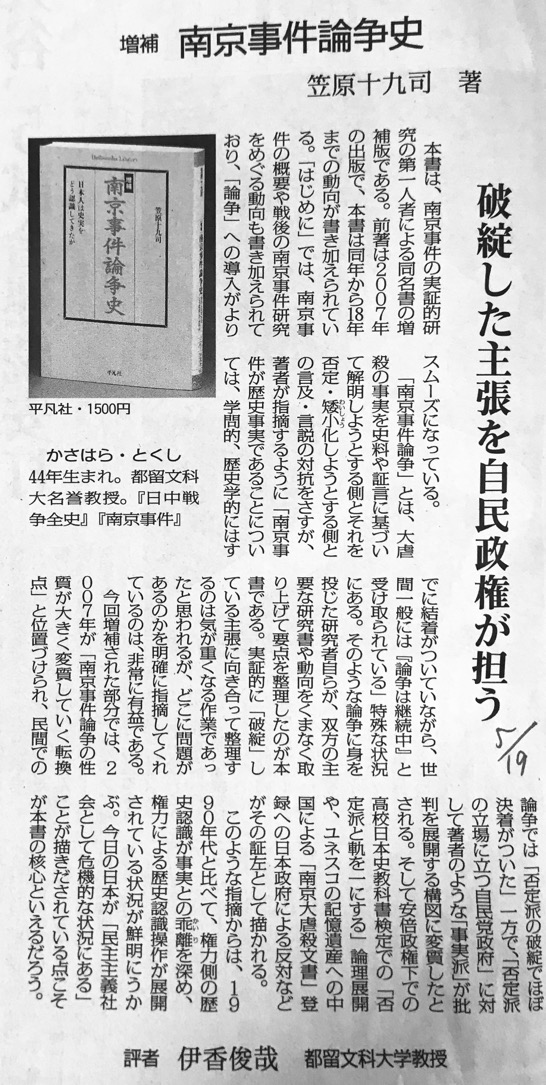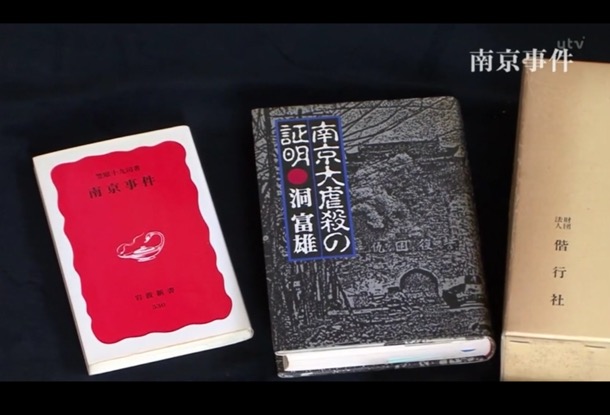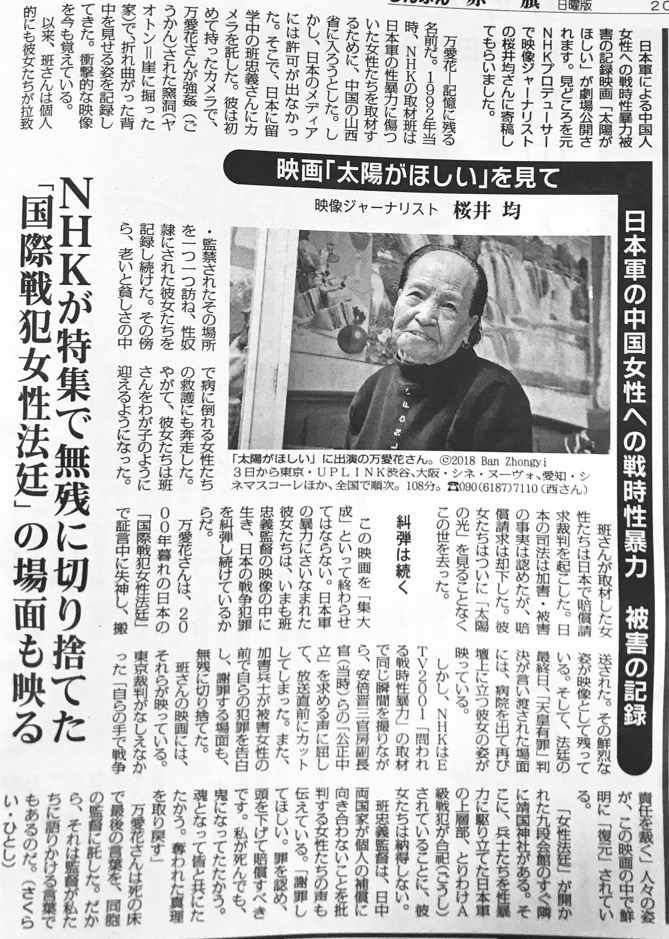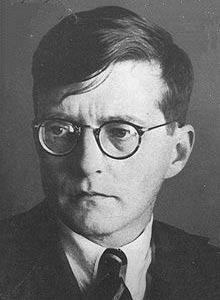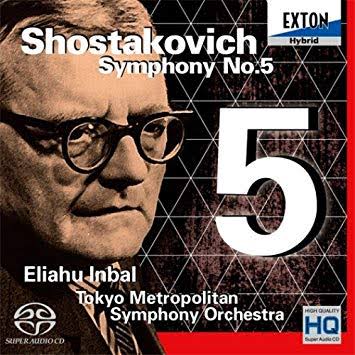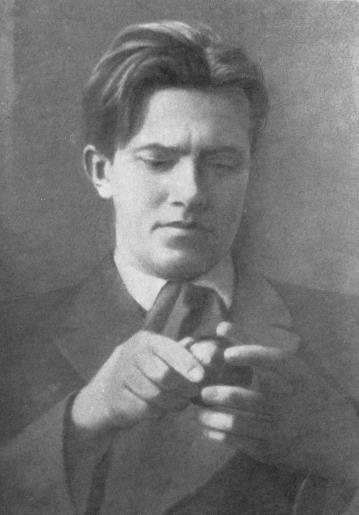江戸時代の先駆的な人びと❶杉田玄白・高野長英・渡辺華山・緒方洪庵・華岡青洲
憲法とたたかいのblogトップ
憲法とたたかいのブログトップ
【このページの目次】
◆杉田玄白・高野長英・渡辺華山・緒方洪庵などリンク集
◆洋学、とくに蘭学による真理の探究の歴史 すす
◆杉田玄白と蘭学事始・解体新書(漫画・蘭学事始抜粋・小学館百科全書)
◆高野長英の生涯(紙芝居・小学館百科全書)
◆渡辺華山の生涯(紙芝居・小学館百科全書)
◆緒方洪庵の生涯と適塾(紙芝居・漫画・小学館百科全書)
◆華岡青洲(漫画・小学館百科全書)
──────────────────────────
🔵江戸時代末期、真理を探究して夜明けを準備した人たち=杉田玄白・高野長英・渡辺華山・緒方洪庵などリンク集
──────────────────────────
🔵当ブログ=江戸時代の先駆的な人びと❷大塩平八郎・安藤昌益・三浦梅園・伊能忠敬その他
🔴【蘭学】

★『ちば見聞録』#001 城下町と蘭学の地~佐倉~(前編)【チバテレビ】21m
★『ちば見聞録』#002 城下町と蘭学の地~佐倉~(後編)【チバテレビ】21m
◆WEB漫画・歴史漫画に緒方洪庵・杉田玄白・華岡青洲
◆戸田=蘭学者たちの遺して くれたものPDF4p
◆飯田 鼎=幕末・維新の時期における知識人, その思想と行動 : 福沢諭吉の書簡集を通じてみる PDF27p
◆音谷 章洋=蘭学塾にみる「和魂洋才」の教育観 PDF 20p
http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/infolib/user_contents/kiyo/111E0000012-24-2.pdf#search=%22%22
🔴杉田玄白・前野良沢






★★ドラマ・風雲児たち・蘭学革命編・解体新書誕生=杉田玄白・前野良沢の生涯 (三谷幸喜シナリオ) 90mhttp://m.pandora.tv/?c=view&ch_userid=kempou7408&prgid=57363518
★★英雄たちの選択・杉田玄白「解体新書」誕生への挑戦58m
★★歴史鑑定・解体新書の誕生=杉田玄白と前野良沢54m
◆◆「蘭学事始」の現代語訳・原文
PDF49p
🔴まんが=私説・杉田玄白「蘭学事始」 http://endlosewelt.web.fc2.com/historia/rgkhtop.html
筆者=よく出来たマンガ、以下抜き書き








★「 杉田玄白の解体新書」『ちょっと学べる!天理図書館の文学ナビ』7m
★杉田玄白(解体新書の逆襲)8m
★【伊集院光】杉田玄白は偉い21m
https://m.youtube.com/watch?v=EhDF6tLatB4
◆松崎=杉田玄白をめぐる人々PDF29+20p
◆松崎 欣=杉田玄白の「〓斎日録」について PDF43p
◆浅原 義雄=蘭学事始 PDF 16p
◆宮永 孝=日本洋学史 : 蘭学事始 PDF63p
◆笠井=杉田玄白『蘭学事始』における学問論PDF6p
◆近代デジタル・ライブラリー=杉田玄白の生涯 : 日本科学の先駆者
中貞夫 著, 木下大雍 絵 (小学館, 1942)
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1719466
◆近代デジタル・ライブラリー=菊池寛 著 蘭学事始 : 他四篇 図書 (春陽堂, 1921)
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/962379
◆近代デジタル・ライブラリー=杉田玄白著・蘭学事始
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/826051
◆石出=江戸幕府による腑分の禁制PDF4p
◆石出=江戸の腑分と小塚原の仕置場PDF7p
◆小川 鼎三=解體新書と蘭学の発展PDF10p
https://www.jstage.jst.go.jp/article/igakutoshokan1954/24/1-2/24_1-2_4/_pdf
◆森良文=蘭学成立の事情について : 『西洋記聞』から『蘭学事始』まで PDF14p
★月刊寺島実郎の世界 2015年1月27日 17世紀オランダ論 杉田玄白 蘭学事始21m
https://m.youtube.com/watch?v=2rHi4rTulXk
🔴高野長英・渡辺崋山




🔵日曜美術館・渡辺崋山
https://drive.google.com/file/d/1_K8H5EeKB4-unmLn-NB79Wb3P9bUF3sC/view?usp=drivesdk
★英雄たちの選択・知りすぎた男たちの挑戦 蛮社の獄 渡辺崋山と高野長英の決断3mお試し
https://www.nhk-ondemand.jp/share/smp/#/share/smp/goods.html?G2015066802SC000
★幕末の蘭学者の足跡 高野長英記念館4m
★ペリー来航 前夜の弾圧 蛮社の獄2m
◆高野長英記念館
http://www.city.oshu.iwate.jp/syuzou01/
◆近代デジタル・ライブラリー=高野長英と渡辺崋山 斎藤斐章 著 (建設社, 1936)
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1037094
◆近代デジタル・ライブラリー=高野長英言行録 杉原三省 編 (内外出版協会, 1908)
◆高野長英の生涯・言行録・年譜
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/781621
★★その時歴史が動いたシーボルト 開国秘話 海を越えた愛 日本を守る43m
https://m.youtube.com/watch?v=7E4MjijpsH0
◆松也の歴史ミステリー–鎖国は抜け道だらけ–長崎–琉球–対馬–松前–シーボルト
◆田原市博物館(渡辺華山)
http://www.taharamuseum.gr.jp/index.html
(渡辺華山)
http://www.taharamuseum.gr.jp/kazan/index.html
◆大月 明=化政・天保期の思想史的一考察 : 渡辺崋山の場合 PDF32p
㊤ http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/infolib/user_contents/kiyo/DBd0040903.pdf#search=%22%22
㊦ http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/infolib/user_contents/kiyo/DBd0051003.pdf#search=%22%22
★★日美 ドナルド・キーン 私と渡辺崋山45m
http://video.fc2.com/ja/content/20130921daeUEtXV/
🔴緒方洪庵


★★その時 歴史が動いた~天然痘との闘い 緒方洪庵・医は仁術なり~43m
または
★★歴史秘話・天然痘とコレラとたたかった緒方洪庵と飢饉とたたかった二宮尊徳
http://m.pandora.tv/?c=view&ch_userid=yhfs8o6q&prgid=60543577&cate=06
🔵英雄たちの選択・衛生国家への挑戦~3人の先覚者たち=緒方・長与・後藤
https://drive.google.com/file/d/1vKD_bzhVXwLVxgSKAr_CDU7LthU_BrLc/view?usp=drivesdk
新型コロナウイルスに揺れる日本。日本人は世界規模の感染症とどう闘ってきたのか?第1回は、日本人の衛生意識の向上に尽力した3人の先覚者に着目する。

(1)幕末、天然痘の治療に革命を起こした緒方洪庵。ジェンナーの種痘→種痘所広げる
(2)その洪庵に学び、明治はじめの時代、コレラ撲滅の陣頭指揮をとった内務省初代衛生局長・長与専斎。適塾→岩倉使節団→衛生行政(衛生=生命をまもる)。清国のコレラ日本へ。コレラ対策→港での検疫→隔離。日清戦争兵士帰還での広がり。
(3)日清戦争後、大陸帰還兵の大規模な検疫を成功させ、世界に日本の衛生力の高さを示した後藤新平。

★郷土に輝く人々 緒方洪庵5m
★緒方洪庵の適塾4m
★花神・適塾の今風景3m
🔷(文化の扉 歴史編)緒方洪庵と感染症医療 コレラ指針いち早く発信/天然痘ワクチン普及
2020年8月3日朝日新聞

テレビドラマ「JIN―仁―」や司馬遼太郎の小説『花神』にも登場する幕末の蘭方医(らんぽうい)で、教育者の緒方洪庵(おがたこうあん)(1810~63)。新型コロナウイルス感染が広がっている今、感染症医療に力を尽くした功績が見直されている。
19世紀の江戸時代末から明治時代初めの日本でもウイルスなどの病原体に起因する感染症が猛威を振るっていた。その代表格はコレラ(虎狼痢〈ころり〉)だった。
コレラが日本で初めて流行したのは文政5(1822)年。鎖国が終わり、外国人との交流が増えたことを背景に、安政5(1858)年、文久2(1862)年と断続的に流行し、数十万人が命を落としたとされる。
この猛威に立ち向かった医師が緒方洪庵である。備中(びっちゅう)国(現岡山県)の足守(あしもり)藩の武士の家に生まれた。大坂で蘭方医の中天游(なかてんゆう)の思々斎塾(ししさいじゅく)に入門し、西洋医学の勉強を始めた。江戸や長崎に遊学し、1838年に大坂で医業を開業。同時に蘭学塾「適々斎塾(てきてきさいじゅく)(適塾〈てきじゅく〉)」も開いた。
教え子は姓名録(門人帳)に記されただけでも636人。一説には数千人に及ぶとされる。将軍の奥医師兼西洋医学所頭取として江戸へ招かれるが、喀血(かっけつ)し、数え54歳で亡くなった。
*
「洪庵は医学と教育という二つの分野で大きな業績を残した」。こう語るのは、洪庵のつくった適塾が源流とされる大阪大学の松永和浩・適塾記念センター准教授(大阪学)だ。感染症対策の業績の一つが、1858年のコレラ流行時に治療指針を示すものとして緊急出版された『虎狼痢治準(ちじゅん)』。3人の西洋医師の書いた医学書を参考にしてわずか5~6日でまとめたもので、医師らに百冊を無料で配った。「感染症には正しい知識の素早い発信が重要であることを、洪庵はよく理解していた」
疱瘡(ほうそう)(天然痘〈てんねんとう〉)の予防にも尽力し、1849年、西洋で確立した天然痘のワクチンを広めるため、大坂に種痘所(除痘館〈じょとうかん〉)を創設。その出張拠点ともいえる分苗所は西日本を中心に5カ月で60カ所以上に達した。幕府に働きかけて実現した種痘医の免許制度は、明治になって実現する医師免許制度の原型となったとされる。
松永さんは「洪庵は患者の治療にあたりながら、不眠不休で『虎狼痢治準』を執筆し、種痘事業では利益を度外視してその普及に努めた。いずれも自分の持てる力を社会のために最大限役立てようとした結果で、私たちはその姿勢に学ぶべきではないか」と話す。
*
日本陸軍の原型をつくった大村益次郎や慶応義塾を創設した福沢諭吉、日本赤十字社初代総裁となった佐野常民(つねたみ)、東京医学校校長や内務省衛生局長を務めた長与専斎(ながよせんさい)……。適塾からは多彩な人材が巣立ったが、それはなぜだろうか。
これまでの研究によれば、適塾では塾生が学力に応じて複数の等級に分けられ、上級者の指導でテキストを輪読することが授業の中心だった。成績に応じて上級に進み、席次も決まるため塾生同士の競争は激しかった。ただし、洪庵が直接指導するのは時折開かれる特別講義ぐらいだったらしい。
洪庵は温厚篤実だったと言われるが、時に「破門だ」などと怒鳴ることも。それをなだめ、塾生を教え諭すのは妻の八重の役割だった。洪庵の書斎の灯火が深夜になっても消えないのを見た塾生たちが自らを戒め、勉学に励んだとの逸話も残る。こうした適塾の教育法を評価する専門家も少なくない。
しかし、『江戸時代の医師修業』の著書がある海原亮(うみはらりょう)・住友史料館主席研究員(日本近世史)は「現在伝えられている適塾の教育は、大半が福沢諭吉の『福翁自伝』を典拠としている。そこに福沢ならではのバイアス(洪庵への畏敬〈いけい〉の念など)がかかっていることを忘れてはならない」と話す。
海原さんは適塾の授業で使われた語学書は当時ではメジャーな教科書で、カリキュラムや授業内容も他の藩校や蘭学塾と大きく違った点はないとみる。「適塾の評価が高いのは塾生の活躍に加え、司馬遼太郎の小説などで描かれた適塾像・洪庵像の影響が大きいのでは。洪庵が優れた医学者・教育者だったのは間違いないが、もっと史料の分析が必要だ」と指摘する。(編集委員・宮代栄一)
■JIN作者「懐の深い人」
洪庵はマンガにも登場する。手塚治虫は曽祖父の手塚良仙が適塾の塾生だったこともあり、「陽(ひ)だまりの樹(き)」で描いた。
「JIN―仁―」の作者でもある村上もとかさんは「グランドジャンプ」に連載中の「侠医(きょうい)冬馬」にも登場させている。「幕府から取り立てられたことを『有難迷惑(ありがためいわく)』とこぼす一方で、貧しく月謝の払えない福沢諭吉に特別の配慮で再入門を許した。懐の深い人だった」と語る。「医術でわからぬことがあった時には、ライバル的な存在だった華岡流・合水堂(がっすいどう)の医師・華岡南洋のもとへ出向いて質問したといわれています。流派にこだわらず、恬淡(てんたん)と真理を探究する姿に(マンガの主人公の)冬馬も強く惹(ひ)かれたのではないでしょうか」
<読む> 緒方洪庵については梅溪昇(うめたにのぼる)『緒方洪庵』(吉川弘文館)や大阪大学適塾記念センター編『新版 緒方洪庵と適塾』(大阪大学出版会)などが詳しい。江戸時代の医塾などについては海原亮『江戸時代の医師修業:学問・学統・遊学』(歴史文化ライブラリー)。
🔵手塚治虫=『陽(ひ)だまりの樹』(手塚治虫の先祖描く)


私の三代前の先祖は手塚良仙といい、大阪の適塾にあって三五九番目の門人として、緒方洪庵に学んだ医者である。
三代前の先祖が、府中藩松平播磨守の侍医だった、ということは、以前からうすうす知ってはいた。ある日突然、日本医史学会の深瀬泰旦という方から、私の論文だが読んでほしい、貴男のご先祖のことを書いた、というわけで「歩兵屯所医師取締役、手塚良斎と手塚良仙」なる小冊子が送られてきた。
それによると、安政二年、良仙は江戸小石川三百坂の家を出て大坂へ向かい、十一月二十五日、適塾の門を叩いたのだった。
その八か月前、適塾には、福澤諭吉が三二八番目の門人として入門しているから、手塚良仙と諭吉とは、いわば”同期の桜”ということになる。
もしや、と思って私は「福翁自伝」をひもといてみた。すると、果たして適塾時代の記述の中に、あった。手塚良仙のエピソードがあった。
手塚良仙は、適塾当時、良庵と名乗っていた。良庵は学問も熱心だったが、なによりも無類の道楽者だったようであった。女遊びにかけては、かなりだらしない男だったらしく、毎夜のような廓通いには諭吉も呆れ果てて、良仙に忠告をして、真面目に勉学をするようにしむけた。しかし女を断った良仙は、諭吉にとっては、どうもおもしろくない。そこで諭吉や同僚はわざと女文字の手紙をでっちあげて、さりげなく良仙に読ませ、良仙がけげんに思って廓へ出向こうとするのをとっつかまえて、寄ってたかって坊主にしようとした。良仙は平謝りに謝って一同に酒肴を振る舞うことで、やっと許してもらった、というエピソードなのである。
無類の女好き、という点では、恐縮だが私の父にそっくりだし、おっちょこちょいでだまされやすい、ということでは私の性格そのままである。読むほどに、やっぱり手塚家の血は、争えないものだと妙に感心した。
(後略)
(日本興業銀行発行 「新開業事情」1986年9月 より抜粋)
◆宮本 又次=緒方洪庵と適塾と大阪の町人社会 PDF26p
🔵緒方洪庵紙芝居
司馬遼太郎原作 〔緒方洪庵生誕200年記念〕http://o-demae.net/library/literary01.html
世の為に尽した人の一生ほど、美しいものはありません。
これから、特に美しい生涯を送った人についてお話します。
それは『緒方洪庵』という人の事です。

この人は、江戸時代末期に生れました。
お医者さまでした。
この人は名を求めず、利益を求めず、溢れるほどの実力がありながらも、他人の為に生き続けました。
そういう生涯は、遥かな山河のように美しく思えるのです。
🔵紙芝居:「洪庵のたいまつ」 その1
〔緒方洪庵〕は、今の岡山県〔足守〕という所で生れました。

父は〔藩〕の仕事をする武士でした。
(洪庵)「父上、私は医者になりたいと思います!」
十二歳の時、突然〔洪庵〕は、父親に言いました。
しかし、父は嫌な顔をしました。
(父)「武士の子は、どこまでも武士であるべきだ!!」
父は〔洪庵〕を立派な武士にしたかったのです。
・・では、なぜ〔洪庵〕は、それほどまで〔医者〕に成りたかったのでしょうか?
それは・・、
〔洪庵〕が子供の時、岡山の地で、《コレラ》という病気が凄まじい勢いで流行しました。

人が嘘のように、ころころ死んだのです。
〔洪庵〕を可愛がってくれた隣の家族も、たった四つ日間の間に、みんな死んでしまいました。
又、当時の《漢方医術》では、これを防ぐ事も治療する事も出来ませんでした。
(洪庵)「私は医者になって、是非人を救いたい。そして出来るなら、漢方ではなく、オランダの医術《蘭方》を学びたい!」
〔洪庵〕は人の死を見ながら、こう決心したのでした。 つづく
🔵しかし、〔洪庵〕の父の許しは遂に出ませんでした。

そこで、〔洪庵〕は16歳の時、ついに置手紙をして家出したのでした。
そして『大阪』へ向かいました。
なぜ、大阪だったかといいますと、その当時、この地で〔蘭方医〕が、塾を開いていたからなのでした。
〔洪庵〕は、この塾に入門して、オランダ医学の〔初歩〕を学びました。
又、幸いなことに、父親も大阪へ転勤となって移って来た為、やがて〔洪庵〕の医学修行も許してくれるようになったのでした。
大阪の塾で、すべてを学び取った〔洪庵〕は、さらに《師》を求めて江戸に行きました。

そして、江戸では『あんま』をしながら学びました。
『あんま』をして、わずかなお金を貰ったり、他家の玄関番をしたりしました。
それは、今でいうアルバイトでした。
こうして〔洪庵〕は、江戸の塾で四年間学び、遂に〔オランダ語〕の難しい本まで読めるようになったのです。
その後、〔洪庵〕は『長崎』へ向かいます。 つづく
🔵長崎・・。

当時、日本は鎖国をしていました。
《鎖国》というのは、外国とは付き合わない、貿易しないという事です。
しかし、長崎の港、一ヶ所だけを、中国とオランダの国に限り、開いていました。
長崎の町には、少しながら、オランダ人が住んでいました。
もう少し、《鎖国》についてお話します。
鎖国というのは、例えば、日本人全部が、真っ暗な箱にいると考えて下さい。
長崎は、箱の中の日本としては、針で突いたような小さな穴で、その穴から、微かに《世界の光》が、差し込んでくる所だったのです。
〔洪庵〕は、この長崎の町で、二年間勉強し、暗い箱の日本から、広く世界の文明を知ろうとしたのです。 つづく
🔵紙芝居:「洪庵のたいまつ」 その4
29歳の時、〔緒方洪庵〕は大阪へ戻ります。

そして、ここで『医院』を開いて、診療に努める一方、オランダ語を教える《塾》も開きました。
ほぼ同時に、結婚もしました。
妻は〔八重(やえ)〕といい、優しく物静かな女性でした。
〔八重〕は、終生〔洪庵〕を助け、塾の生徒たちから、母親のように慕われました。
〔洪庵〕は、自分の塾の名を、自分の号である〔適々斎〕から取って、《適塾(てきじゅく)》と名付けました。

《適塾》は人気が出て、全国からたくさんの若者たちが集まって来ました。
《適塾》は、素晴らしい学校でした。
門も運動場もない、普通の二階建ての〔民家〕でしたが、どの若者も、勉強がしたくて、遠くからはるばるやって来るのです。
江戸時代は、身分差別の社会ですが、この学校はいっさい平等で、侍の子も、町医者の子も、農民の子も、入学試験無しで学べました。
塾へは、多くの学生達が入学して来ましたが、先生は〔洪庵〕一人です。
〔洪庵〕は、病人たちの診療をしながら教えなければならないので、体が二つあっても足りませんでした。
それでも塾の教育は、うまくいきました。
それは、塾生のうちで、よくできる者が、できない者を教えたからでした。 つづく
🔵その5
・・・余談ながら、(わぁ~司馬遼調)僕は大学生の頃、三回ほどこの〔洪庵〕さんの作られた『適塾』に見学に行っている。
今は中に入れるのかどうかは知らないが、昔(今から25年ほど前)は、見学できた。(僕の家からは自転車でも行けた)
ほんとにこの狭い民家の中で、たくさんの学生達が、不眠不休で勉強していたのかと思うと、感動しまくりだった。(柱に刀傷もあったなぁ。ストレス溜まってたんやろなぁ・・)
僕は、村田蔵六(のちの大村益次郎)が、試験が終る度に、この『適塾』二階の物干し場に出て、豆腐をアテに酒を飲み、試験後の疲れを癒していたと小説『花神』で読み、実際、(オンボロになっていた)物干し場に出てみて、感動したのを覚えている。
この『適塾』、のちの『大阪大学 医学部』の卒業生で、この大学の教授になられた枚方市のホスピス医〔南吉一〕師と、のち御一緒に「紙芝居」を作る事になろうとは、その時、まだ知らなかった・・。(これも司馬遼調のパクリです)

(紙芝居の続き・・)
〔洪庵〕は、自分が長崎や江戸で学んだ事を、より深く、熱心に教えました。
〔洪庵〕は、常に学生たちに向かってこう言いました。
「君たちの中で、将来、医者に成る者も多くいるでしょう。
しかし、医者という者は、とびきりの親切者以外は、成ってはいけない。
病人を見れば、『可哀想でたまらない』という性分の者以外は、《医者》に成る資格は無いのです。
医者がこの世で生活しているのは、人の為であって、自分の為ではありません。
決して、有名に成ろうと思わないように。
又、お金儲けを考えないように。
ただただ、自分を捨てて人を救う事だけを考えなさい。
又、オランダ語を勉強したからといって、医者にだけ成る必要はありません。自分の学んだ《学問》から、人を生かし、自分を生かす道を見つけなさい。」と・・。 つづく(次回、最終回)
🔵その6
・・このような《教育方針》でありましたので、適塾からは、さまざまな分野の『達人』たちが生れました。

幕末の戦争で、敵味方の区別なく傷を負った兵士を治療した『日本赤十字』の創始者や、又、今や壱万円冊の顔となった慶応義塾大学の創立者〔福沢諭吉〕など、多くの偉人たちを輩出しました。
やがて、そのような〔洪庵〕の評判を聞きつけた《江戸幕府》は、「是非、江戸に来て、『将軍』様専門の医者(奥医師)になってくれ」と言ってきます。
それは、医者としては目もくらむような名誉な事でした。
しかし、〔洪庵〕は断りました。
「決して、有名になろうと思うな。」という、自分の戒めに反する事だったからです。
しかし幕府は許さず、・・・ついに〔洪庵〕は「もはや断りきれない。討ち死にの覚悟で参ろう。」と、いやいや大阪を出発しました。
江戸に行った〔洪庵〕は、その次の年、そこであっけなく亡くなってしまいます。
もともと病弱であったのですが、江戸での華やかな生活は、〔洪庵〕には合わず、心の長閑さが失われてしまったのが原因でした。
江戸城での、〔しきたり〕ばかりの生活に気を使いすぎ、それが彼の健康を蝕み、命を落とさせたのでした。

振り返ってみると、〔洪庵〕は、自分の恩師達から引き継いだ、《たいまつの火》を、より一層大きくした人だったのでしょう。
彼の偉大さは、自分の《火》を、弟子たち一人ひとりに移し続けた事でした。
弟子たちの《たいまつの火》は、後にそれぞれの分野で、明々と輝きました。
やがて、その火の群れは、日本の《近代》を照らす大きな明かりとなっていったのです。
後生の私達は、〔洪庵〕に感謝しなければならないでしょう。
緒方洪庵、享年54歳。
おしまい
★[朗読]司馬遼太郎 – 洪庵のたいまつ
(前編) https://m.youtube.com/watch?v=ePjlDn-VH0Y
(中編) https://m.youtube.com/watch?v=4oD936REQ7I
(後編)なし
🔴華岡青州




🔵知恵泉・華岡青洲=世界で初めて全身麻酔45m
https://drive.google.com/file/d/1BP7DMFA9WG-Wf2pJLGl1BHNATnat2uc1/view?usp=drivesdk
★★歴史列伝・世界初の全身麻酔手術を行った華岡青洲
http://www.veoh.com/m/watch.php?v=v116363581AN4DTM4j
★★世界初全身麻酔薬を完成させた日本人医師華岡青洲の壮絶で感動のドラマ計23m
❶ https://m.youtube.com/watch?v=oCWkjVSaoNs
❷ https://m.youtube.com/watch?v=D5LdmOVD3T4
★★華岡青洲の妻(昭和42年)映画プレビュー23m
https://m.youtube.com/watch?v=7TlcN5Dk8UU
★★華岡青洲の妻(演劇)計50m
❶ https://m.youtube.com/watch?v=HBmaiT0ppwI
❷ https://m.youtube.com/watch?v=X2ij2wLoK9g
❸ https://m.youtube.com/watch?v=uzPPlOc-yek
❹ https://m.youtube.com/watch?v=MV3g4iJZOBg
【豊後・中津でのルイス・アルメイダの西洋医学の伝播】
(前野良沢学ぶ)
★★風之荘「円相」29西洋医学28m
🔴9706岩波新書・佐藤昌介=高野長英.pdf
🔴7201高橋しん一=洋学思想史論(1).pdf
🔴7201高橋しん一=洋学思想史論(2).pdf
🔴7206かもしか文庫・加藤文三=学問の花ひらいて-蘭学事始のなぞ.pdf
🔴9706岩崎=日本近世思想史序説㊦②洋学=杉田・司馬・渡辺・高野.pdf
────────────────────────────
🔵洋学、とくに蘭学による真理の探究の歴史
────────────────────────────
16世紀中ごろ、キリスト教の布教とともにポルトガル人、スペイン人によって始まったが、これは南蛮学、蛮学などとよばれた。やがて江戸幕府が鎖国政策をとったことにより、西洋の学術・文化は、日本への渡来を許された唯一の西洋の国オランダが長崎出島(でじま)に建てたオランダ商館を通じて、オランダ語を介して移入されることになり、これは蘭学(らんがく)とよばれた。鎖国政策が緩み、開国政策がとられた幕末期になると、オランダ人以外の諸外国人も渡来するようになり、イギリス・フランスなどの学術・文化が、それぞれの国の言語とともに渡来した。洋学ということばはこの時期以降に一般化した。洋学は自然科学・社会科学・人文科学の広い分野で西洋の知識・学問を移入するのに力を発揮したが、ことに英学が蘭学にかわって主要な地位を占めた。[大鳥蘭三郎]
◆蘭学のはじまり
江戸時代にオランダを通じ、またはオランダ語を介して日本に伝わった西洋の学問・技術の総称。鎖国政策の下の江戸時代に、日本渡航を許可されていた唯一の西洋国家であるオランダは、日本との貿易を営むための商館を、17世紀の初めに長崎出島(でじま)に建て(初めは平戸(ひらど))、厳しい制限を受けてはいたが盛んに西洋の文物を日本に伝えた。
蘭学を内容的にみれば、医学、天文学、兵学などの自然科学系統に属するものが主であったが、これは鎖国以前の南蛮(ポルトガル、スペイン)を経由して日本に伝えられた西洋学術の名残(なごり)とも考えられる。西洋学術の伝承にあたった人々はオランダ側ではオランダ商館医師が主役で、そのほかに商館長・書記なども関係し、日本側ではオランダ通詞(つうじ)が役職上からも当然中心であり、そのほかは特別な許可を得た有志の者であった。長崎を中心に行われた蘭学は、オランダ商館長一行が、最初は年に1回、1790年(寛政2)からは4年に1回行う江戸参府が刺激となって、江戸その他の地でしだいに広く行われるようになった。[大鳥蘭三郎]
◆揺籃期の蘭学
初期のころの蘭学はいわゆる見よう見まねの程度のものにすぎなかったが、明らかに西洋学術書の影響がみられる。たとえば、医学における楢林鎮山(ならばやしちんざん)の『紅夷(こうい)外科宗伝』、天文における北島見信(きたじまけんしん)の『紅毛天地二図贅説(ぜいせつ)』などはいずれもその成果であるといえる。8代将軍徳川吉宗(よしむね)の西欧科学の奨励、殖産興業の政策は、1740年(元文5)ついに青木昆陽(こんよう)、野呂元丈(のろげんじょう)の2人に命じてオランダ語を学ばせるに至った。これが大きな契機となって、杉田玄白(げんぱく)がいう本格的な蘭学がおこり、杉田玄白、前野良沢(りょうたく)、中川淳庵(じゅんあん)、桂川甫周(かつらがわほしゅう)らによるクルムスの人体解剖書の翻訳事業が1771年(明和8)に始まり、74年(安永3)に日本で最初の西洋医学書の翻訳である『解体新書』(4巻)が出版された。この書の出現は日本の医学にとってまさに画期的なことであった。そしてこれが蘭学そのものに対しても大きな推進力となった。
杉田玄白・桂川甫周に蘭学を学んだ宇田川玄随(げんずい)、前野良沢・杉田玄白に蘭学の教えを受けた大槻玄沢(おおつきげんたく)はともに大いに蘭学に励み、ついに杉田家・桂川家と並んで江戸の蘭学四大家と称せられるに至った。宇田川玄随は日本最初の西洋内科書『西説内科選要』を訳述し、大槻玄沢は『蘭学階梯(かいてい)』を著し、蘭学者としての地位を固めた。これとほぼ同時期に、長崎の通詞たちによるオランダ語研究も本格的に行われるようになり、西善三郎、本木仁太夫(もときにだゆう)(良永(よしなが))、志筑(しづき)忠雄、馬場佐十郎らの優れた蘭学者が輩出した。[大鳥蘭三郎]
◆民間学者の活躍
江戸に主流を発した蘭学は、その後、宇田川・大槻の門下から出た人々によってしだいに京都・大坂をはじめとする諸地方へと広がっていった。ここで目につくのは、これら蘭学を率先して研究した人々は、桂川甫周を除いて、他はいずれもいわば民間の学者あるいは陪臣の医者であったことである。これは蘭学のもつ一つの大きな特徴であるが、幕府当局もようやく蘭学に対する認識を改め、1811年(文化8)天文方に新たに蕃書和解(わげ)御用の一局を設け、外国文書の翻訳に備えた。馬場佐十郎・大槻玄沢の2人が訳員に任ぜられ、オランダ書籍の翻訳にあたった。2人はとりあえずショメルの百科全書の蘭訳本の重訳に着手した(翻訳事業は翻訳者がかわりながら1846年(弘化3)まで続き、『厚生新編』と題された)。またこのころに、当時のオランダ商館長ドゥーフが長崎のオランダ通詞数人とともにハルマの蘭仏対訳辞書の和訳を試み、その第一稿が成り、蘭日辞書(『道訳法爾馬(ドゥーフ・ハルマ)』、別名『長崎ハルマ』)ができあがった。これによって蘭学は新しい段階を迎えたが、オランダ以外の諸外国との折衝が複雑化するにつれて、英語、ロシア語、その他の外国語の研究が行われるようになり、蘭学のもつ意味がそれまでのものとはすこしずつ変わってきた。そして洋学ということばが生まれ、使われるようになった。この時期、西洋医学書の翻訳・出版と並んで、志筑忠雄の『暦象新書』、帆足万里(ほあしばんり)の『窮理通(きゅうりつう)』、青地林宗(あおちりんそう)の『気海観瀾(きかいかんらん)』、川本幸民の『気海観瀾広義』、宇田川榕菴(ようあん)の『舎密開宗(せいみかいそう)』『植学啓原』など、天文学、地理学、物理学、化学、植物学などの西洋学術の新知識が蘭学者によって伝えられた。[大鳥蘭三郎]
◆シーボルトの影響力
日本に渡来した多くのオランダ商館医師のなかには、西洋の学問・技術を日本に伝えるという面で積極的に活動した人も少なくない。ケンペル(1690来日)、ツンベルク(1775来日)らはその例であるが、1823年(文政6)に来日したシーボルトほど大きな足跡を日本に残した人はなかった。シーボルトは在日中に多くの日本人門下生を養成したばかりでなく、『日本』『日本植物誌』『日本動物誌』などを著し、積極的に日本をヨーロッパに紹介したことでも、とくに記憶されるべき人である。なお、1828年シーボルトの帰国に際して起こった事件(シーボルト事件)は、その後、思想的に蘭学者を束縛するきっかけとなった。また平賀源内・高野長英ら進歩的な蘭学者による幕府批判が弾圧された「蛮社の獄」(1839)も、その後の洋学者に大きな影響を及ぼした。蘭学の時代の後期に、大坂に開かれた緒方洪庵(こうあん)の適々斎塾(適塾)は優れた蘭学者を多く輩出し、明治時代の各界に多数の人材を送り込んだことは特筆されるべき業績といえる。[大鳥蘭三郎]
◆蘭学から英学へ
蘭学を介して行われてきた諸外国との折衝は、やがて直接的にそれぞれの国と交渉せざるをえなくなり、蘭学は一転して国防のための研究として行われるようになり、多分に軍事科学化した。一方、鎖国―開国、攘夷(じょうい)―通商と相反する主張が激しく戦わされるようになると、蘭学は本質的には開国の側にたったが、実際には幕府当局および諸藩の軍備充実のために大いに利用された。開国の国是が定まると、多くの外国人が渡来するとともに、オランダ語以外の外国語も伝えられ、ことに英語が非常な勢いで広まっていった。しかしそれでもオランダとオランダ語は大きな影響力を維持し続けていたといえる。
1855年(安政2)オランダから蒸気船を贈られたのを機として長崎に海軍伝習所が設けられ、オランダから招かれた海軍将兵がそこの教官となって、海軍に関する諸学を教授した。また同所に57年に招かれたオランダ海軍軍医のポンペが公に西洋医学を教授した。さらにその年、江戸に蕃書調所(ばんしょしらべしょ)が開かれ、箕作阮甫(みつくりげんぽ)・川本幸民らの蘭学者が教授方に任命され、蘭学の教授と研究にあたった。その翌年には江戸に種痘所(しゅとうしょ)(後の西洋医学所)が開設され、教授・解剖・種痘の3科に分けて、西洋医学の研究が行われた。中央におけるこのような蘭学をめぐる諸施設が置かれるに伴い、薩摩(さつま)(鹿児島)、肥前(ひぜん)(佐賀・長崎)、長門(ながと)(山口)、越前(えちぜん)(福井)の各藩にも同様のものが開かれ、盛んに西洋文化の移入が試みられた。
このように蘭学は、開国後もなおしばらくの間は、来日した諸外国の間で中心的な地位を保っていたが、しだいにその地位を他に譲り、主として英学が盛んになるのと反比例して影響力を弱めていった。しかし江戸時代から明治初期に欧米諸国の文化を日本に移入し、吸収するうえで蘭学が果たした役割は大きく、日本文化に与えた影響は著しかった。[大鳥蘭三郎]
『板沢武男著『日蘭文化交渉史の研究』(1959・吉川弘文館) ▽沼田次郎著『洋学伝来の歴史』(1960・至文堂) ▽佐藤昌介著『洋学史の研究』(1980・中央公論社)』
────────────────────────────
🔵杉田玄白の生涯、蘭学事始・解体新書
───────────────────────────
◆◆まんが=私説・杉田玄白「蘭学事始」
(杉田玄白の生涯も含めよく出来ている)
http://endlosewelt.web.fc2.com/historia/rgkhtop.html
◆◆WEB漫画=杉田玄白(上記まんがとは別のまんが)
◆◆杉田玄白
(福井の歴史)
http://rekishi.dogaclip.com/2015/07/post-bbeb.html
◆蘭学との関わり
杉田玄白(すぎたげんぱく)は、小浜藩の医者の子として江戸で生まれ、18歳から幕府医官の西玄哲(にしげんてつ)のもとで蘭方外科を学びました。
また、平賀源内(ひらがげんない)らと同時代の人でもあり、蘭学に興味を持ちました。
オランダ商館長の通訳であった西善三郎(にしぜんざぶろう)に会い、オランダ語の難しさを知り学問を一時あきらめたこともありました。
しかし、西洋の解剖学の本『ターヘル・アナトミア』との出会いが、玄白を再びオランダ語へと向かわせたのでした。
◆翻訳を思い立った理由
小浜藩医をしていた父の後を継いで侍医(じい)になった玄白(げんぱく)は、『ターヘル・アナトミア』という西洋の解剖学の本(オランダ語版)を手に入れました。
オランダ語はさっぱり分かりませんが、日本や中国の五臓六腑(ごぞうろっぷ)の図とは異なるその付図(ふず)を、本物の人体と比べたいという思いが募(つの)りました。
39歳の時に江戸で死体の解剖に立ち会う機会を得て、付図の正確さに驚きこの本を翻訳して世に役立てようと決心したのです。
◆翻訳のエピソード
玄白(げんぱく)は、小浜藩医の中川淳庵(なかがわじゅんあん)や前野良沢(まえのりょうたく)らと共に『ターヘル・アナトミア』の翻訳を行いました。
満足な辞書もない時代で、「眉(まゆ)というものは眼の上方にあるものなり」という一文すら、丸一日かかっても分からない有様(ありさま)でした。
それでも1ヶ月に7回ほど集まって勉強し、動物の解剖を行ったり、通訳の者に聞いたりしながら、11回もの書き直しと足かけ3年の歳月をかけて完成しました。
「軟骨(なんこつ)」や「神経」といった言葉は、この時に彼らがつくったものです。
◆『蘭学事始』の出版
『蘭学事始(らんがくことはじめ)』は玄白(げんぱく)が83歳の時、翻訳業の苦労の軌跡(きせき)を回想して記し、大槻玄沢(おおつきげんたく)に送った手記です。
玄白は蘭学の開拓者として、自分の死によって蘭学草創(そうそう)の事を知るものがいなくなることを惜しみ、当時の事を書き残したのです。
江戸時代は写本のみで伝わりましたが、幕末の頃にこの写本を読んだ福沢諭吉(ふくざわゆきち)が泣いて感動し、学問の継承・保存の為にこの本を世に出版。一般に読まれるようになりました。
◆玄白ゆかりの地
小浜市には、玄白(げんぱく)が小浜藩出身だったことにちなんで名前がつけられた「杉田玄白(すぎたげんぱく)記念 公立小浜病院」があります。
病院正面には玄白の銅像があり、生前の玄白を忠実に再現して建てられました。
ほかにも小浜市には、小浜で亡くなった玄白の兄と義母の墓がある空印寺(くういんじ)や、玄白の父が納めたと伝わる弁天像がある羽賀(はが)寺など、ゆかりの地があります。
──────────────────────────
🔵「蘭学事始」の抜粋
(現代語訳・原文「蘭学事始」から)
──────────────────────────
◆現代の蘭学ブーム
昨今、世間に蘭学ということがひろく行われ、真面目な人は熱心に学び、無知でいい加減な人たちはただむやみに恐れ入ったり半可通で吹聴しています。ところでその蘭学の起 源をみると、昔、私が仲間たち 二三人がこの仕事にいわば偶然に志を抱いて開始したもの で、それからはやくも五十年近く経ちました。ここまで盛んになろうとは到底思わなかっ たのに、こうなったのは不思議です。
漢学は大昔、遣唐使たちを異国の中国へ遣わし、或は英邁の僧侶が渡来して、直接相手 の国の人について学び、帰朝後に貴賤上下へ教導のために行ったので、少しずつ盛んにな ったのは理解できます。
蘭学では、こんな風に人を相手の国に派遣した例はありません。それなのにこれほど盛 んになったのは何故か考えると、医療の場合は教えが大衆への実務を優先する故、それだ け会得しやすかったのでしょう。また、事が新奇なだけに従来と違う妙術もあると世人も 考え、さらにはずるがしこい一派がこの名前で、利を図るために流布した面もありそうで す。
◆鎖国の歴史の概略を
昔からの歴史をいろいろ考えと、天正慶長の頃(1573-1591, 1596-1614)、西洋の人がだんだんと日本の西部に船をつけたのは、表向きは交易が名目ですが、蔭には別の欲望もあったようです。故に、その災いが発生してわが国では初めての大事件として、厳禁してしまったわけで、この点はよく知られています。この邪教の問題は、ここでは問題外として 議論はしません。但し、その頃の船に乗って来た医者から伝来した外科の流儀は世に残りました。いわゆる南蛮流です。
その前後より、オランダ船も入港を許可され、肥前平戸へ来ていました。外国船がすべ て禁止となった時も、オランダには宗教的野心がないとして、引続き渡来を許されました。 そこから三十三年目、長崎出島の南蛮人を追放して、その跡へオランダ人を移し、その後 は年々長崎の港にオランダ船は入れることになりました。
それが寛永十八年(1641)で、その船でやって来た医師に、またかの国の外科治療法を 伝えた者も多く、オランダ流外科と称しています。といっても、横文字の書籍を読んで習 い覚えたのではなく、ただその手術を見習い、その薬方を聞き、書き留めただけです。そ の上、わが国では入手できない薬品も多く、代りの薬で患者を治療しています。
(訳註:蔭には別の欲望:キリスト教布教のことを指す。玄白は明示を避けているようだ。 南蛮:ポルトガルとスペインのこと。)
◆オランダ語と通詞たち
徳川の当初、西洋関係についてはいろいろありましたが、すべて厳しく禁止されまし た。渡来が許可されたオランダ関係も、彼らが使う横書きの文字の読み書きは禁止され、 通詞の人たちも片仮名で書き留めるだけで、口から口へ記憶して通訳の用を足し、それが 長年のやり方でした。それで、横書きの文字を読み習おうという人は誰一人いませんでし た。ところが、どんなことも時期がくれば、自ら開けるというものです。
八代将軍吉宗公の時、長崎のオランダ通詞西善三郎、吉雄幸左衛門、今一人何某(名は忘 れた)の三人が申し合せて議論し、以下の結論を出しました。
「これまで通詞の家で一切の御用を取扱ってきているが、オランダ文字を知らず、ただ暗 記の言葉だけで通訳し、複雑な数多い用事をなんとか果たして勤めているのは、あまりに 頼りない。せめて自分たちだけでも横文字を習い、かの国の書物も読む免許を受けたい。 そうすれば、以後は万事につけて事情が明白になり、用事を果たしやすいはずだ。今のやり方ではあの国の人に偽り欺かれても、これを糾明する方法もない。」
そう考えて、三人で言葉を合わせて申し立て、どうぞ免許を許可して欲しいと、公に願い出ました。これが至極尤もな願いとして聞き届けられ、早速許可されました。オランダ船の渡来から百年余で、横文字を学ぶことの初めです。
◆ターヘル・アナトミア登場
明和八年辛卯(1771)の春と記憶していますが、中川淳庵が例の宿泊所へ行き、オランダ人がターヘル・アナトミアとカスバリュス・アナトミアという身体内景図説の書二本を取 り出して、希望者に譲ろうというのを持ち帰って、私に見せました。もちろん一字も読め ませんでしたが、臓腑、骨節などの描写が見事でこれまで見聞したのとはまったく異り、きっと実際に解剖して描いたものと感じ、是非欲しいと思いました。そもそもわが家はオ ランダ流の外科を唱える身でもあり、せめて書棚に備えて置きたいのです。しかし、当時 の我が家は貧しく、これを購入する力がなかったので、藩の太夫である岡新左衛門という 人の許に持って行って、こんなわけで是非この蘭書が欲しい、入手したいのだが手元不如意で残念と話すと、新左衛門がこれを聞いて、それは入手しておいて役に立つものか、役 に立つものならお殿様に費用を出して貰うよう取計うといいます。私は、必ずこんな風に 役立つという目当はないけれども、将来きっと役立つに相違ないと考えるので見てほしい と答えました。傍に倉小左衛門(後に青野と改む)という男が居て、それはなんとか調べてみよう、杉田氏はこれをムダにする人ではないと助言してくれました。これにより、容 易に願いが叶い、望みとおり入手できました。私が蘭書を手に入れた最初でした。
さて、それまで平賀源内などと語り合って、いろいろ見聞して、オランダの測定法や 物理学などは驚き入ることが多く、もしこうした図書の内容を理解して解釈できるなら、きっと格別の利益が得られるはず、しかしこれまでそこを志す人がないのは残念で、何と かこれを切り開く道はないだろうか、江戸では到底ダメでも、長崎の通訳に頼んで判読して貰いたいものだ、一冊でも翻訳という仕事が完成すれば、大変な国益とも成るはずだ、だけどなあ・・・と力の及ばない点を毎度嘆息していました。しかし、この慨嘆は決 してむなしく終わらなかったのです。
◆腑分けをみる
その頃、この解剖書を入手したので、先づその図を実物に照して見たいと考えるようになりました。
まさに、それを学ぶ時がきたというべきか、何とも不思議なめぐり合わせです。三月三日の夜、時の町奉行 曲淵甲斐守殿の家士 得能万兵衛という男から手紙がきて、明日お抱え 医師の何某という者が、千住骨ケ原で解剖を行うから、希望ならこちらへ来して欲しいと 知らせてきました。同僚の小杉玄適氏は、以前京都で山脇東洋先生の門で学び、山脇先生 の企画した解剖に参加しており、先生について実際に視てみると、昔の人の話は全部うそで信じるわけにはいかないと前から述べていました。昔は 9 臓と称し、その後は5臓6腑と分けているが、それがそもそも杜撰さの証拠だそうです。
東洋先生は、すでに蔵志という著書も出版していました。私はこの書も見ており、機会が あれば自分でも解剖を是非みたいと思っていました。たまたまオランダの解剖書も手に入 ったことでもあり、照合して何とかその実否を確認したいと考え、この誘いを喜んで格別 の幸運だと早速でかけるつもりでうきうきしました。ところでこんな幸運は独り占めすべ きではないと、仲間たちで関心の深そうな人々に知らせるつもりで、先づ同僚中川淳庵を 初め誰彼と知らせた中で、例の良沢にも知らせました。
良沢は私より年齢が十歳ほど上で自分より老輩です。知り合いでしたが、通常は交流も稀 で直接交渉は乏しかったのですが、医学の問題に熱心なことは互いに知っており、腑分けから漏らすわけにはいきません。早速知らせたいのに時間がさしせまり、しかもオランダ 人が滞留中で、夜になってしまいました。急に知らせる便もなく、どうしようかと考えて、 臨時の思い付きで、明朝これこれがあり、お望みなら早朝に浅草三谷町出口の茶屋まで御 越し下さい、私もそこでお待ちしますと書いて、とりあえず手紙を書き、知った人と相談 して本石町の木戸際に居た辻駕の者を雇って、置いてこいと命じました。
翌朝支度を整えて約束の場所へ行くと良沢も来ており、他の仲間も皆集まって出迎えました。そこで良沢が蘭書を一冊懐中からとり出し、開き示しながら、これはターヘル・ アナトミアというオランダの解剖書で、先年長崎へ行った時に手に入れて、家にしまって おいたと言います。見ると、私がつい最近手に入れた蘭書とまさに同書同版です。これこそ奇遇だと、互いに手を打って感嘆し合いました。 しかも良沢は、長崎遊学の際に、その地で習ったといって、本を開いて、これはロングといって肺のこと、こちらはハルトといって心臓のこと、マーグというのは胃で、ミルトと いうのは脾臓だと指して教えてくれました。どれも漢説の図とはまったく違い、誰もがとにかく直接見ないうちはと、心中で疑いをもっていました。
(略)
◆腑分けを見ての帰路
帰路は、良沢、淳庵と私と、三人同行です。途中で語り合いながら、さてさて今日の実 験にはまったく驚いた、これまで気付かなかったのは恥づかしい、いやしくも医師として 主君に仕える身で、その医術の基本である人間の形態の本当の姿を知らず、今まで毎日こ の仕事を勤めて来たのは面目ない次第だ、どうか今日のこの実験に基づき、大体でも身体 の真理を知って医療を行えば、この仕事で身を立てる申訳もたつだろうと、共々嘆息しま した。
良沢も、まったくその通りで自分も同感だと述べた。
その時、私はこう述べました。何とかしてこのターヘル・アナトミアの一部を新たに翻訳 すれば、身体内外のことがわかり、今後の治療に役立つだろう、何とかして通訳等の手を かりず、読んでいきたいとの発言でした。これに対して良沢が言うには、自分は年来蘭書 を読みたいという宿願を抱いていたが、同じ考えの良友がなく、常々その点をを嘆きなが ら日を送ってきた、参加者の方々が是非読みたいという強く望まれるなら、自分は先年長 崎へもゆき、蘭語も少々は知っているから、それを核として、一緒に何とか読もうではな いかといいます。それを聞くと淳庵と私は、それは何とも嬉しい、皆で力を合わせて、是非頑張って読んで行こうと答えました。
良沢はこれを聞くと本当に大喜びしました。それなら善はいそげという諺もあるから、早 速明日私宅へいらして欲しい、何とか工夫しようと深く約束して、その日は参加者それぞ れの宿所へと帰りました。
◆決断
さてこの書を読みはじめるに際して、どうやって文章にしていこうかと話し合いまし た。はじめから身体の内部のことはとてもわかりにくいだろう、本の冒頭部分に、身体の 前面と後面の全体図があって、これは体表面です。これなら、名前はみなわかっているから、この図と説明の符号を照らし合せて考えるのなら、取付きやすいはずで、本の最初の 図でもあり、みんなで先づここからスタートして翻訳を開始しようと定めました。解体新 書形体名目篇というのがこれです。
その頃はデ(de)とか、へット(het)とか、またアルス(als)、ウエルケ(welke)等 の助詞の類さえ、何が何やら気持の上で明確には解釈できず、たとえ少しだけ覚えている 単語があっても、前後が一向にわからないことだらけでした。例えば、眉(ウエィンブラーウ)というのは目の上に生えた毛だという一句もぼんやりしかわからず、長い春の一日 かけても明確にならず、日暮れまで考へ詰め、互いににらみ合って、僅か一二寸ばかりの 文章、一行も解釈できなかったりしました。
或る日、鼻のところで、フルへッヘンドしているものとあるのをみて、この単語がわかりません。これは何を意味するのだと考え合ったものの、どうもなりません。その頃ウヲ ールデンブック(辞書)はなく、良沢が長崎で入手したオランダ語の簡略なパンフレット がありそれを探すと、フルへッヘンドの説明に、木の枝を断ちると跡がフルへッヘンドと なり、また庭を掃除すると塵土が集まってフルへッヘンドするなどと書いてありました。 どんな意味だろうかと、また例の如くこじつけ考え合うものの判断がつきません。この時、 私の意見で、本の枝を断った跡が治癒するとうずたかくなる、また掃除して塵土が集まる とこれもうずたかくなる、鼻は顔の真ん中で堆起しているから、フルへッヘンドは堆(ウ ヅタカシ)ということだろう、この単語は「堆」と訳してはどうだろうというと、参加者は この提案を聞いて、それは素晴らしい、堆(ウヅタカシ)と訳せばあてはまると決定しました。その時の嬉しさといったら、何に譬えようか、連城の玉を得たというか、とんでもない宝物を手に入れた気持でした。
◆十轡(くつわ)十文字=解らない用語のマーク
こんな風に推理しては訳語を定めていきました。次第に解釈できる単語の数も増し、良沢がすでに知っていた訳語集を増補しました。その中にも、シンネン(精神)などいう単語が出でくるなど、何とも解釈できないのもありました。こういうのは後でわかるまでと りあえず符号を付けて置こうと、丸の中に十文字を書いておき、この符号のつく「わからないこと」を、轡(くつわ)十文字と名づけた。毎回いろいろに申し合せ、いくら考えても 解らないことがあって、その苦しさの余りに、それもまた轡十文字、これもまた轡十文字 となりました。そういいながら、仕事を進めるのはもちろん人で、成功不成功は天運との 喩で辛苦しました。
一ケ月に六七回の割合で、こんな風に頭をつかい、根をつめて仕事を進めました。定例の 日には誰もサボらず、わけもなくして参加者と相集まり会議して読み合って、わからないことも繰り返すとわかると言うとおりで、一年も過ぎた頃には訳語もかなり増加し、読む につれてかの国の事態も自然と了解でき、そうなると難しい言葉の少ないところは、一日 に十行も、あるいはもっと多くも、格別の労苦なく解釈できるようになりました。一方で、毎年はじめに江戸にくる通訳の人たちに尋ねて確認したこともありました。その間にも、 さらに解剖を観察したこともあり、動物を解剖して図と照らし合わせたことも何回もあり ました。
◆翻訳が順調に進む楽しさ
この会の業務を怠らずに勤めていると、次第に同じ興味を抱く人たちの参加者が増えてきましたが、各自考えがいろいろで一様ではありません。
私は偶然この解剖書を手に入れ、直ちに実際の解剖で確認し、東西千古の差があると知って驚いて心服し、書物の内容をなんとか早く解明して、治療の実用に役立て、世の医家の仕事に一日も早く一部でも役立たせいという気持ちで、他に望みはありません。それで、 一日の会合で解釈できた分はその夜翻訳して草稿にし、その際に訳述の仕方を種々考え直しました。こうして四年の間に、草稿は十一度書き換え板下に渡せるまでになり、遂に解 体新書翻訳の事業が完成しました。
そもそも江戸でこの学を創業して、腑分と言い古した用語を新たに「解体」と訳し直し、また仲間の誰がいうともなく蘭学という新名を提唱し、日本全国に自然と広まって通称と なりました。現在の隆盛のきっかけです。今から考えると、これまで二百年間、外科法は 伝わったものの、直接オランダの医書を訳すことはなく、この時の私たちの初めての仕事が、不思議にも医道の根本である解剖書で、それが新訳の起点となったのは、偶然ながら 実に天意です。
昔をふりかえると、新書が完成する前に、こんな風に努力勉励を二、三年続けて、そ の状況がわかるに随い、さとうきびを囁むが如く、次第にその甘味に喰いつき、これで千古の誤も解け、その基本がたしかに理解できるのが楽しく、集会の日は前日から夜の明けるのを待ちかね、子供がお祭に出かけるような気持でした。
そもそも当時の江戸には華やかさに浮かれる風俗もあり、他の人も私たちの話を聞き伝えて、雷同して仲間入りするものもいました。その時の人々を思うと、最後までいた人も 途中で脱落した人も、今は皆あの世にいっています。嶺春泰、烏山松円などは本当によく 出席してくれましたが、今はもう世を去っています。
(略)
◆翻訳における玄白の態度基本を教えたい
私は元来おおざっぱな人間で学問も乏しく、オランダ学説を翻訳しても、読者がそれをどんどん理解し解釈するのを助ける力はありません。しかし、人に頼んだのでは自分の意 図も通じないので、やむをえず無知も顧みずに自分で書き綴りました。だからこそ、細か い面では知識や認識が不足して見苦しい面もあり、精密で微妙な意味もありそうと思いな がら解釈できず、いい加減とは知りながら、強いて解釈しないで放置し、意味のわかった ところだけを書きました。
たとえば京に上る場合、東海道と東山道の二道あることを知って、西へ西へと行けば、 終には京に上り着きます。そんな基本の道筋を教えるのが重要と思い、大体の基本を書いたわけです。その手初めとして、世の医師の為に翻訳を開始したのです。元来学問不足の 自分だから翻訳の仕方は知らず、ましてオランダ書の翻訳となれば、例のない仕事で、読 み初めたばかりで、細密な判読できません。しかし何度もくりかえすように、医師たるも の先づ第一に臓器の構造やその形や働きを知らないでは済まず、是非その意味を知らせて、 診療の助けにしてほしいというのが狙いです。
意図がそうだから、訳をいそいで早くその大筋を人の耳にも留まり理解し易くして、従 来の医書に比較して異なる点を速かにさとらせるのを第一としました。それ故、従来の漢字で表現する旧名を用いて訳したいと思いました。ところが、漢字の名とオランダ語の名 とは一致しないものも多く、方針が決まらずに当惑しました。あれこれ考え合せ、自分に も初めてで、とにかくわかりやすいことを狙おうと決し、時に翻訳、時に対訳、時に直訳、時に義訳と、さまざまに工夫しました。義訳とは意味から単語をつくること、直訳とはオ ランダ語をそのままカナ表記することをいいます。とにかく、ああ書いたりこう書いたり して、昼夜自分で書き直し、前にもいったように草稿は十一度書き換え、四年かけてよう やく完成しました。
その時点では、オランダの風俗の細かい面、微妙な点などは今ほど明らかではありませ んでした。ですから、いろいろと判明した現時点から見ると、誤解が多いかもしれません。 しかし、物事を最初に唱える時は、後からそしりを受けるのを恐れては何も出来ません。くりかえしますが、基本にもとづいて合点できた点を訳出したのです。経典の梵語からの漢訳も、四十二章経から始まってようやく現在の一切経に達しました。このやり方が、私の当初よりの希望であり、願いです。
良沢という人がいなかったら、この道は到底開けなかったでしょう。しかし、一方で私 のように基本に忠実だがおおまかな人間がいなければ、この道がこれほど速かには開かれなかったでしょう。この組み合わせも、天の助です。
(略)
◆各種の地ならし:各方面への献本
「解体約図」が先に完成し、ついで本篇の「解体新書」も出版されましたが、紅毛談さえ 絶版になった前例があり、西洋のことはかりそめにも唱えてはならぬと言われると困りま す。オランダは別格として貰えるかも不明瞭で、差支えないと判定されると断定もできま せん。秘密出版扱いされて、禁令を犯したとして罪を受ける可能性も否定できず、この問 題は重大な恐怖でした。
横文字をそのまま出したのではなく、読めば内容は明確で、医道解明のためだから差支えないと自分で判断して、初めての翻訳を公にすると唱おうと、覚悟を極めて決断しました。といっても、何しろ翻訳出版としては最初で、何とか神の庇護を受けたく、一部を公儀 へ献本しました。幸い仲間の桂川甫周君の父上の桂川甫三君が旧友で、彼の判断をきいた ところ、彼が取扱って推挙して御奥から将軍に献上してくれました。それで特に問題も生じずに済んだのは、幸いでした。 次に私の従弟の吉村辰碩が京都に住んでおり、彼の推挙で関白九条家と近衛准后内前公と広橋家へも一部づつ献上しました。これによって、三家より目出度き古歌を自ら書いた ものを頂戴し、また東坊城家よりは七言絶句の詩を賦して頂戴しました。また時の大小御 老中方へも同じく一部づつ進呈しました。こちらも何の障害もなく経過しました。こうして安堵して、オランダ翻訳書がいよいよ公けになりました。
(略)
◆最後に
一滴の油を広い池にたらすと、それが散って池全体に及びます。前野良沢、中川淳庵、 私の三人が申し合わせ、かりそめに思いついた仕事が、五十年近い歳月を経て、日本中に 広まり、毎年訳説の本も出ています。「一犬虚を吠ゆれば万犬実を伝う」という言葉は、一 人が嘘をいうと廻りがそれを真実として伝えるというデタラメですが、蘭学はその逆で「一 犬実を吠ゆれば万犬虚を吠ゆる」で、はじめに真実から出発したからその後も真実の道は 失われません。もちろん、翻訳書の中には良いものも悪いものもあるでしょうが、それは 一応問題の外におきましょう。これだけ長生きすると、今日のような隆盛を見聞して、喜 んだり驚いりたりです。現在この領域の仕事をする人で、これまでのことを種々に聞き伝 え語り伝えを誤る人も多そうなので、あとさきながら覚えて居た事柄をこんな風に書きま した。
かえすがえすも、実に嬉しいことです。この道が開ければ百年後千年後の医家は真理を 得て、人々の救済に役立つに違いないと踊りだしたい気持ちです。私は幸い長命で、自分 の知る蘭学を開いた初めから、今の隆盛まで実見できて、身に備わった幸いです。ゆっく り考えれば、何よりも世の中が太平だからです。世に篤好厚志の人があっても、戦乱で騒 がしい社会では学業を創建し、隆盛に導く余裕はとうてい望めません。
◆◆杉田玄白
すぎたげんぱく

(1733―1817)
小学館百科全書
江戸中期の蘭方医(らんぽうい)、蘭学者。名は翼(よく)、字(あざな)は子鳳、斎(いさい)のち九幸(きゅうこう)と号し、玄白は通称。学塾を天真楼といい、晩年の別邸を小詩仙堂(しょうしせんどう)という。若狭(わかさ)国(福井県)の小浜(おばま)藩酒井侯の藩医杉田甫仙(ほせん)の子として江戸の藩邸中屋敷に生まれ、難産であったため、そのとき母を失う。宮瀬竜門(りゅうもん)(1720―1771)に漢学を、幕府医官西玄哲(1681―1760)に蘭方外科を学び、藩医となる。同藩の医師小杉玄適を通じ、山脇東洋(やまわきとうよう)の古医方の唱導に刺激を受け、また江戸参府のオランダ商館長、オランダ通詞(つうじ)吉雄耕牛(よしおこうぎゅう)(幸左衛門)らに会い、蘭方外科につき質問し、やがてオランダ医書『ターヘル・アナトミア』を入手した。1771年(明和8)春、前野良沢(りょうたく)、中川淳庵(じゅんあん)らと江戸の小塚原(こづかっぱら)の刑場で死刑囚の死体の解剖を実見した。その結果『ターヘル・アナトミア』、正しくはドイツの解剖学者クルムスJohann Adam Kulmusが著し、オランダのディクテンGerardus Dicten(1696ころ―1770)のオランダ語訳した『Ontleedkundige Tafelen』(『解剖図譜』)の精緻(せいち)なるを知り、同志とともに翻訳を決意して着手する。4か年の努力を経て、1774年(安永3)『解体新書』5巻(図1巻・図説4巻)を完成し、刊行の推進力となった。この挙は江戸における本格的蘭方医書の翻訳事業の嚆矢(こうし)であって、日本の医学史上に及ぼした影響すこぶる大きく、その後の蘭学発達に果たした功績は大きい。彼ら同志の翻訳の苦心のありさまは晩年の追想『蘭学事始(ことはじめ)』に詳しい。主家への勤務をはじめ、多数の患者を診療し、患家を往診する余暇に、学塾天真楼を経営し、大槻玄沢(おおつきげんたく)、杉田伯元、宇田川玄真(1770―1835)ら多数の門人の育成に努めた。また蘭書の収集に意を注いで、それを門人の利用に供するなど蘭学の発達に貢献した。前記の訳著のほかに奥州一関(いちのせき)藩の医師建部清菴(たけべせいあん)との往復書簡集『和蘭(おらんだ)医事問答』をはじめ、『解体約図』『狂医之言』『形影夜話(けいえいやわ)』『養生七不可(ようじょうしちふか)』などにおいて医学知識を啓蒙(けいもう)し、『乱心二十四条』『後見草(あとみぐさ)』『玉味噌(たまみそ)』『野叟独語(やそうどくご)』『犬解嘲(けんかいちょう)』『耄耋(ぼうてつ)独語』など多くの著述を通じて、政治・社会問題を論述し、その所信を表明した。
彼の日記『斎日録』をみると、「病論会」なる研究会を定期的に会員の回り持ち会場で開催して、医学研鑽(けんさん)に努めたようすをうかがうことができる。若いころに阪昌周(さかしょうしゅう)(?―1784)に連歌(れんが)を習って、自ら詩歌をつくり、宋紫石(そうしせき)、石川大浪(たいろう)(1765―1818)ら江戸の洋風画家たちとも交わって画技も高かったことは、その大幅で極彩色の「百鶴(ひゃっかく)の図」をはじめとして、戯画などを通じてうかがい知ることができる。
蘭方医学の本質を求めて、心の問答を展開した相手建部清菴の第5子を養子に迎え、伯元と改称せしめ家塾を継がせた。実子立卿(りゅうけい)には西洋流眼科をもって別家独立させ、その子孫には成卿(せいけい)・玄端(げんたん)ら有能な蘭学者・蘭方医が輩出、活躍している。石川大浪が描いた肖像は老境の玄白像をよく伝えている。文化(ぶんか)14年4月17日、江戸で病没、85歳。墓は東京都港区虎ノ門、天徳寺の塔頭(たっちゅう)、栄閑院(通称猿寺)にあり、東京都史跡に指定されている。[片桐一男]
『片桐一男著『杉田玄白』(1971/新装版・1986・吉川弘文館)』
◆蘭学事始
らんがくことはじめ

杉田玄白の回想録。上下二巻。1815年(文化12)4月、当時83歳の杉田玄白が、日蘭交渉の発端から筆をおこし、蘭学創始をめぐる思い出と蘭学発達の跡をまとめたもの。なかでも、同志前野良沢(りょうたく)、中川淳庵(じゅんあん)らとともにオランダの解剖書『ターヘル・アナトミア』の翻訳から、『解体新書』出版にかけての苦心談は有名である。玄白は自筆草稿を大槻(おおつき)玄沢に示し、訂正を依頼した。玄沢は玄白より伝聞したところと自らの見聞をも加え、玄白に聞きただしながら整備、完成して、「蘭已(すで)に東せしとやいふべき起源」を記してあるところから『蘭東事始』と題して玄白に進呈したというが、覚えやすいということから「蘭学事始」の題名にかえたともいう。江戸時代には『蘭東事始』『和蘭事始』の書名で写本のまま伝わった。67年(慶応3)のころ神田孝平がみつけた古写本をもとに、杉田廉卿(れんけい)とも協議して、福沢諭吉が、69年(明治2)、木版本として刊行するに際し、『和蘭事始』を『蘭学事始』の書名に改めた。以来『蘭学事始』の名が一般に知られるようになり、岩波文庫に収められるようになっていっそう普及した。[片桐一男]
『緒方富雄校訂『蘭学事始』(岩波文庫)』
◆解体新書
かいたいしんしょ


小学館百科全書
解剖学書。日本最初の本格的な西洋医学の翻訳書。本文4冊、別に序文と図譜を掲げた1冊からなる。1774年(安永3)刊。日本で初めてのこの翻訳事業の中心になったのは前野良沢(りょうたく)と杉田玄白(げんぱく)で、中川淳庵(じゅんあん)・桂川甫周(かつらがわほしゅう)ら多くの人々が協力した。1771年(明和8)から4年間にわたる苦心・努力のさまは、杉田玄白の回想録『蘭学事始(らんがくことはじめ)』のなかに詳細かつ新鮮に記されている。
一般に『ターヘル・アナトミア』とよばれている原書は、正しくは、ドイツのクルムスJohann Adam Kulmusが1722年に著した『解剖図譜』Anatomische Tabellenを、ライデンのディクテンGerardus Dictenがオランダ語訳した『Ontleedkundige Tafelen』(1741)で、杉田玄白らが依拠したのはその第2版であった。これは小型本で、その内容は簡単な本文とやや詳しい注記からなり、27枚の図譜を付した初学者向きの医書である。『解体新書』は全文漢文で記述され、原書の本文だけを訳出し、注記は訳していない。図譜は小田野直武(なおたけ)が描き、原書は銅版であるが、本書は木版である。付図の数は原書よりやや多くなっているが、それは他の西洋医学書からも引用したことによる。図譜を掲載する冊子には、ほかに吉雄耕牛(よしおこうぎゅう)の序文と杉田玄白の自序、および凡例が載っている。[大鳥蘭三郎]
『三枝博音編『復刻 日本科学古典全書 第8巻』(1978・朝日新聞社) ▽酒井シズ訳『解体新書』(1978・講談社)』
◆前野良沢
まえのりょうたく

(1723―1803)
日本洋(蘭(らん))学の開祖。中津藩医。名は達、諱(いみな)は熹(よみす)(余美寿)、字(あざな)は子悦・子章、通称を良沢、号は楽山。なお別号蘭化は、藩侯が良沢のオランダ語研究の熱心さを庇護(ひご)し戯れに和蘭の化け物と称したことによるもの。1723年(享保8)筑前(ちくぜん)藩士谷口新介の子として江戸牛込矢来(うしごめやらい)に生まれた。幼時、父を亡くし母に去られ孤児となり、山城(やましろ)国(京都府)淀(よど)藩医官で伯父の宮田全沢(『医学知律』の著者)に育てられた。宮田は「他人が捨てて顧みないようなことに愛情をもち、世に残すよう心がけよ」と説き聞かせた。良沢はやがて中津藩医前野東元の養子となり、吉益東洞(よしますとうどう)流医学を修めた。一方宮田の訓育方針に従い、当時すでに廃れかかっていた一節切(ひとよぎり)の竹管器に習熟し、さらに猿若狂言(中村座の家狂言)の稽古(けいこ)にも通っていた。オランダ語の学習も当時では珍奇に属することであったが、同藩の坂江鴎(さかこうおう)に蘭書の残編を見せられたがわからず、同じ人間のすることがわからぬことはないと志をたてたのが始まりという。1769年(明和6)『和蘭文字略考』の著をもつ青木昆陽の手ほどきを受け、翌1770年長崎へ赴きオランダ通詞吉雄幸左衛門(よしおこうざえもん)(耕牛)・楢林栄左衛門(ならばやしえいざえもん)(1773―1837)・小川悦之進らについて学び、『マーリン字書』や解剖書『ターヘル・アナトミア』などを購求し江戸に帰った。江戸参府のカピタンや商館医を宿舎長崎屋に訪ねもした。1771年3月4日江戸千住小塚原(こづかっぱら)での死刑囚の腑分(ふわ)けを杉田玄白(げんぱく)・中川淳庵(じゅんあん)らと参観、ヨーロッパ人の解剖書の図の正確さを認め翻訳を決意、翌日から築地(つきじ)鉄砲州の中津藩邸内の良沢役宅で開始。知識・年齢に先行する良沢が盟主に推され、自作の『蘭訳筌(せん)』を同志に示しながら推進、1774年(安永3)8月『解体新書』全5冊を公刊した。しかし良沢は自分の名を出すことを拒否。訳後、同志と離れオランダ語学研究とオランダ書翻訳に専念した。語学書『蘭語随筆』『字学小成』『和蘭訳文略』『和蘭訳筌』などのほか、天文書『翻訳運動法』『測曜(ぎ)図説』、カムチャツカについて『東砂葛記』、ロシアの歴史『魯西亜(ロシア)本紀』『魯西亜大統略記』、『和蘭築城法』、良沢の識見を随所にみせるヨーロッパの諸事項の評書『管蠡秘言(かんれいひげん)』など、諸学啓蒙(けいもう)訳書を著した。また、高山彦九郎や最上徳内(もがみとくない)と交流し、大槻玄沢(おおつきげんたく)、江馬蘭斎(えまらんさい)(1747―1838)、小石元俊らの指導にもあたった。享和(きょうわ)3年10月17日没。墓は東京都中野区の慶安寺。1893年(明治26)正四位を贈られた。[末中哲夫]
『岩崎克己著『前野蘭化』(1938・私家版/全3巻・平凡社・東洋文庫)』
───────────────────────────
🔵高野長英の生涯
───────────────────────────
🔷🔷紙芝居=高野長英の生涯


(高野長英記念館)

1 江戸時代は、外国との往来が、禁止されていました。長崎の出島が、世界に開かれたたった一つの窓口でした。この出島に、1823年、シーボルトがやってきました。
シーボルトの噂を聞いた人々が、日本の各地から、長崎にやってきました。
この物語の主人公、高野長英も、シーボルトから医学と蘭学を学んだ一人でした。

2. やがて、江戸にもどった長英は、医者になり、蘭学の塾も開きました。
そして、渡辺崋山と出会い、「尚歯会」に参加しました。尚歯会には、武士や医者の他に、お坊さんや町人まで、身分の違う多くの人々が集まっていました。

3. さて、オランダから幕府にとどいた情報によると、イギリスの船が、近々、日本にやってくるそうだ。漂流民を日本に送る理由だが、通商を求めてくるとの噂もあった。幕府は、外国船打払い令を盾に、この船を追い払うことに決めた。
世界の様子を勉強していた尚歯会の人々は、これを聞いてびっくりしました。

4. 「漂流した者たちを、親切に、送り届けるというのに、大砲を打ち込むとは、何ということだ。そんなことをしたら、どんな災難が日本にふりかかるか分かったものではない。そうだ、世界の様子を知らせる本を書こう。幕府の取り決めが間違いであることを知ってもらおう。」と長英は考え、夢物語を書きました。

5. ところが、目付け、鳥居耀蔵は、無人島に渡ろうとしたという罪をでっちあげ、渡辺崋山や高野長英を訴えました。
もともと、鳥居耀蔵は、西洋を研究する蘭学者をきらっていた。この機会に、「蘭学を広める者どもを手痛い目にあわせ、ねだやしにしてやろう。」と考えたのでした。

6. こうして、夢物語を書いた長英は、「幕府の政治を批判し人々を惑わした」という罪に問われ、今でいう無期懲役にあたる永牢を言い渡されました。
長英は、牢屋から無実を訴え続けますが、許されませんでした。

7. そして6年が過ぎたある夜のこと。牢屋が火事になり、長英は牢から解き放されました。3日の間に戻れば、罪が軽くなる定めでしたが、長英は、ついに戻らなかったのです。

8. 故郷では、母が長英の身を案じていました。このとき、母は前沢の茂木家に身を寄せ、水沢の高野家には孫に当たる能恵がひとり残されていました。

9. 江戸から逃亡した長英は、密かに故郷を訪ねました。6年ぶりの親子の再会ですが、落ち着いて話をする暇はありません。長英は、母の幸せを祈りつつ、早々に旅立たなければなりませんでした。

10. 母との再会を果たした長英は、門人や学者の仲間に助けられ、幕府の追及を逃れて旅を続けました。

11. 危険な旅を続けながらも、長英は、病気に苦しむ人をいつも忘れませんでした。病人の治療や薬をつくったりもしました。

12. 四国に逃れていたある日、長英は名高い金比羅神社に参拝しました。
ここで、長英は、「アジアの第一人者になる」と誓います。そして、幕府の目を逃れ、広島、大坂、名古屋と旅を続けました。

13. 江戸に戻る決心をした長英は、顔を薬で焼き、人相を変えます。

14. 顔を変え、名前も沢三伯と改めた長英は、大胆にも、江戸で病院を開き、蘭学の勉強を続けます。

15. しかし、ここにも蘭学を弾圧する幕府の手は伸びてきました。10月30日、遂に、長英の家に、奉行所の捕りかたが踏込みました。長英は思わず、短刀に手をのばし、後ろから襲い掛かる捕り方に切りつけました。しかし、抵抗むなしく、長英は、のどをついて覚悟の自殺をします。長英46才の最後でした。

16. 長英の友人、江川英龍は、夜明けの富士山を描き、「里は、まだ、夜深し、富士の朝ぼらけ」との言葉を書き添えました。
しかし、日本の人々は、いつまでも目を塞がれてはいませんでした。高野長英や渡辺崋山などの尊い努力によって、日本の夜明けは、もうそこまで近づいていたのです。(完)
◆◆高野長英
たかのちょうえい
(1804―1850)
小学館百科全書
江戸後期の蘭学(らんがく)者、思想家。名は譲、号は瑞皐(ずいこう)、通称卿斎(けいさい)。文化(ぶんか)元年奥州水沢(岩手県奥州(おうしゅう)市)に生まれる。仙台侯の一門伊達将監(だてしょうげん)の家臣後藤介実慶(そうすけさねのぶ)の三男(母は侍医高野玄斎の妹美代)。9歳のとき父実慶が死亡し、母方の伯父高野玄斎(1771/1775―1827)の養嗣子(ようしし)となる。玄斎は杉田玄白の門人。17歳で兄堪斎(たんさい)(?―1823)に同行して江戸に遊学、杉田伯元(はくげん)(玄白の養子)の門に入る。やがて杉田塾を辞し、吉田長叔(ちょうしゅく)(1779―1824)の内弟子となり、オランダ医学を修めた。19歳の1822年(文政5)通称を長英と改め、日光、筑波(つくば)山地方において採薬に従事するとともに蘭文法の研究を始める。1825年長崎に赴き、シーボルトの鳴滝(なるたき)塾に入る。23歳で蘭語論文をシーボルトに提出し、ドクトルの称号を受けた。平戸(ひらど)藩主松浦(まつら)侯の援助で『シケイキュツデ』(化学書)20巻の翻訳に着手し、またシーボルトの依頼により和文蘭訳の業にも従った。養父の訃報(ふほう)に接するも病気を理由に帰郷を拒む。
1828年シーボルト事件が起こるや長崎から逃亡。以後広島、尾道(おのみち)、大坂を経て京都で開業した。同地より親戚(しんせき)にあて、高野家相続権を放棄し、また他家に禄仕(ろくし)しないことを誓う。これは西洋生理学研究を続けたいがためであった。1830年(天保1)江戸に戻り、麹町(こうじまち)貝坂で開業、かたわら生理学研究を進める。1832年『西説医原枢要』内編5巻を脱稿。渡辺崋山(かざん)の住む半蔵門外田原藩邸に近かった関係で崋山の依頼による蘭書の訳述を行い、崋山や江川英龍(ひでたつ)らと尚歯(しょうし)会に参加して交際を深めた。1837年上州、常総地方に出張し、洋学を講じ診療を行う。1838年『戊戌(ぼじゅつ)夢物語』を草し、幕府の異国船撃攘(げきじょう)策を批判する。この冬、妻ゆき(経歴未詳)と結婚。翌1839年尚歯会グループに加えられた弾圧事件、蛮社(ばんしゃ)の獄で崋山が『慎機(しんき)論』および『西洋事情書』による幕政批判の罪で召喚されるや、いったん姿を隠すも、北町奉行(ぶぎょう)所に自首する。獄中『わすれがたみ』を著し無実を訴えるが、『戊戌夢物語』による幕政批判の罪で永牢(えいろう)の判決を受ける。1841年牢名主(ろうなぬし)となり、『蛮社遭厄(そうやく)小記』を草し郷党に送る。翌1842年赦免出獄を画策するも効なく、1844年(弘化1)40歳にて非人栄蔵に放火させ、小伝馬(こでんま)町の牢舎から脱獄、鈴木春山の庇護(ひご)の下に江戸市中に潜伏。その間、春山の兵学書翻訳を助ける。この年、長男の融(とおる)が生まれた。1847年『知彼一助』を宇和島藩主伊達宗城(むねなり)に献上、『三兵答古知幾(タクチーキ)』を訳了。1848年(嘉永1)伊達宗城に招かれ宇和島(愛媛県宇和島市)に行く。伊藤瑞渓(ずいけい)の名で蘭書を教授し、『家(ほうか)必読』などの兵書を翻訳する。同年宇和島を去り、広島を経由し、のち江戸に再潜入。高橋柳助、沢三伯の名で医業を営むも、嘉永(かえい)3年10月捕吏に襲われ自刃。47歳。
彼の思想は、シーボルト門下の第一人者として、蘭語学、蘭医学を通し西洋近代学術の方法と知識を身につけていた点にある。そのため伝統的封建教学である朱子学に対決し、林述斎(じゅつさい)の次男鳥居耀蔵(とりいようぞう)ら守旧派による弾圧を招いた。しかし、やがて長英らの洋学は文明開化期の知的革命に受け継がれ、近代化に大きく作用した。この点は藤田茂吉(ふじたもきち)(1852―1892)『文明東漸史』(1884)の指摘にも明らかであり、高く評価されなければならない。[藤原 暹]
『佐藤昌介校注『高野長英』(『日本思想大系55』所収・1971・岩波書店) ▽『高野長英全集』全6巻(1978~1982・第一書房) ▽佐藤昌介著『高野長英』(岩波新書)』
◆夢物語
ゆめものがたり
小学館百科全書
江戸後期の蘭学(らんがく)者高野長英(ちょうえい)が1838年(天保戊戌9)10月21日に、渡辺崋山(かざん)の『慎機論(しんきろん)』と同様、イギリス船モリソン号来日に対する幕府の撃攘(げきじょう)策に反対して執筆した警世の書である。正しくは『戊戌(ぼじゅつ)夢物語』という。構成は、冬の夜ふけゆくままに、長英がひとり書を読む間に、夢となく幻となく恍惚(こうこつ)の世界に入る。そこは、ある人の家に数十人の学者が集まり、時事問題を論じている場である。やがて甲と乙とがモリソン号について問答をし始める。甲の問いに乙が答える内容は、モリソン号に代表される(ただし船名を人名と誤っている)イギリスの国勢の情報で、とくにアジア、中国への交易進出問題である。鎖国下にある日本に対して漂流民送還を口実に開国を迫っている現状を述べ、これを撃退せんとする打払令に反対した。この書は執筆後まもなく転写され、かなりの反響をよんだらしく、『夢物語評』『夢々物語』等が出た。39年蘭学者の弾圧事件である蛮社の獄が起こると、長英は本書による幕政批判の罪で永牢(えいろう)の判決を受けた。[藤原 暹]
『佐藤昌介校注『戊戌夢物語』(『日本思想大系 55 高野長英他』所収・1971・岩波書店)』
◆シーボルト
没年:1866.10.18(1866.10.18)
生年:1796.2.17
江戸後期に来日したドイツ人の医師,生物学者。バイエルンのビュルツブルクの医師の家に生まれる。ビュルツブルク大学で医学,植物学,動物学,地理学などを学び,1820年学位を得る。1822年,オランダ領東インド会社付の医官となり,1823年にジャワに赴任,まもなく日本に任官することになり,文政6(1823)年8月に長崎出島に入った。はじめ商館の内部で,やがては市内の吉雄幸載の私塾などでも,診療と講義を行っていたが,翌年長崎奉行から許されて,郊外の鳴滝に学舎を造った。学生の宿舎や診療室,さらには薬草園まで備えたこの鳴滝塾に,週1回出張したシーボルトは,実地の診療や医学上の臨床講義のみならず,様々な分野の学問の講義を行い,小関三英,高野長英,伊東玄朴,美馬順三,二宮敬作らの蘭学の逸材を育てた。 文政9年オランダ商館長の江戸参府に随行して1カ月余り江戸に滞在。その間,高橋景保,大槻玄沢,宇田川榕庵ら,江戸の蘭学者とも親しくなった。そこにいわゆる「シーボルト事件」の種子が芽生える。長崎へ帰ったシーボルトと高橋や間宮林蔵らとの交際のなかで,間宮が疑惑を持ったのをきっかけに,同11年に任期が満ちて帰国するシーボルトの乗った船が嵐によって戻された際に,荷物が調べられて,国禁違反が発覚。高橋がシーボルトの『フォン・クルーゼンシュテルン世界周航記』とオランダ領のアジア地図などと引き換えに,伊能忠敬の『日本沿海測量図』のコピーなどをシーボルトに渡していたこと,そのほかにも葵の紋服などをシーボルトが持ち出そうとしていたことが明らかになって,高橋は裁判の途中に獄中で死亡,シーボルトも国外追放となり,同12年12月に日本を去った。 ヨーロッパに戻ったシーボルトは,日本関係の書物を次々に発表して,日本学の権威としてヨーロッパで重要視されるようになった。またオランダ国王を動かして幕府に開国を勧める親書を起草し,この親書は弘化1(1844)年に幕府に伝えられたが,幕府はこれを拒否,さらに,日本が開国した際にヨーロッパ諸国と結ぶべき条約の私案を起草してオランダ政府に伝え,この条約案は嘉永5(1852)年にクルティウスに託されて幕府の手に届いている。開国後,クルティウスはシーボルトに対する追放の解除を幕府に要請,安政5(1858)年日蘭修好条約の締結とともに実現,同6年シーボルトは念願の再来日を果たした。しかし文久2(1862)年に維新の成立をみぬまま日本を去り,ミュンヘンで亡くなった。再来日に際して帯同していた長男のアレクサンダーは,そのまま日本に留まり,イギリス公使館通訳,明治3(1870)年以降は政府のお雇いとして,外交政策などの相談役となり,次男のハインリヒも同2年に来日,外交官として長年日本に滞在した。さらに長崎時代に日本の女性楠本其扇(お滝)との間に生まれた楠本イネは,のちに産科医として知られるようになった。 シーボルトの学問的業績は,医師として臨床面で日本の人々に大きな福音を残し,さらに多くの蘭医を育てたことは,高く評価されなければならないが,それにもまして重要なのは,ヨーロッパに彼によって紹介された日本の風物である。最も重要なのは,通称『日本』もしくは『日本誌』すなわち『日本とその周辺諸地域(蝦夷,南千島,樺太,朝鮮,琉球)についての記述集成』としてライデンで1832年から54年までかかって刊行されたもので,日本についての浩翰で巨大な総合的研究書である。このほか『日本動物誌』(1833~50),『日本植物誌』(1835~70)は学問的に貴重な業績である。
◆シーボルトと高野長英
22歳の時に長崎のシーボルトを訪ねて鳴滝塾で学び続ける。鳴滝塾におけるシーボルトの教育方針は、弟子たちに日本研究をさせて発表させるというものであった。シーボルトが持ち帰った弟子たちのオランダ語論文43点のうち11点は長英の論文であった。
長英の論文は、「活花の技法について」、「日本婦人の礼儀および婦人の化粧ならびに結婚風習について」、「小野蘭山『飲膳摘要』(日本人の食べ物の百科全集)」、「日本に於ける茶樹の栽培と茶の製法」(2)、「日本古代史断片」、「都における寺と神社の記述」、「琉球に関する記述(新井白石『南島志』抄訳)などで、日本の歴史、地理、風俗、産業などシーボルトの日本研究の基礎資料となるものであった。
長英は「鯨油および捕鯨について」という博士論文を書きシーボルトよりドクトルの称号を受ける。
シーボルトはドイツ人であったが、オランダ人になりすまして日本に滞在した。日本地図を持ち出そうとして幕府の禁に触れ、スパイ容疑で国外追放となる。いわゆる「シーボルト事件」である。
弟子たちはシーボルトのスパイ行為を助けたとしてこの事件に連座する。
たまたま旅行中で難を逃れた長英は、長崎を離れ江戸に行く。
<参考文献>呉秀三『シーボルト先生其生涯及功業』(東洋文庫),板沢武雄『シーボルト』
(村上陽一郎)
◆蛮社の獄
ばんしゃのごく
江戸後期、蘭学(らんがく)者に対する弾圧事件。蛮社とは蛮学社中の略。三河(愛知県)田原(たはら)藩の家老渡辺崋山(かざん)は、藩政改革の推進を図って、高野長英(ちょうえい)、小関三英(こせきさんえい)ら蘭学者と尚歯(しょうし)会の集まりを通じて西洋知識の吸収に努めていた。また、幕臣・諸藩士などの識者のなかには、崋山の識見を慕って集まる者も少なくなかった。大学頭(かみ)林述斎(じゅっさい)の子で目付の鳥居耀蔵(とりいようぞう)は、儒教思想による守旧的立場から、崋山ら蘭学者を憎悪していた。1837年(天保8)6月、対日通商の望みをもって、日本人漂流民の送還のため江戸湾に入ったアメリカ船モリソン号が、浦賀で異国船打払令によって撃退されるという事件が起きた。すると、崋山は『慎機論(しんきろん)』を、長英は『戊戌(ぼじゅつ)夢物語』(『夢物語』)を著して、世界情勢に目を覆い人道に反する幕府の処置を批判した。39年、老中水野忠邦(ただくに)は守旧派の鳥居と開明派の伊豆韮山(にらやま)の代官江川英龍(ひでたつ)に江戸湾の備場(そなえば)巡見を命じた。江戸に帰った江川から意見を求められた崋山は、江戸湾防備の意見書や『西洋事情書』などを江川に送った。鳥居は、江川が崋山と親しいことを知り、崋山が無人島(小笠原(おがさわら)島)渡航計画に関係し、長英らと蘭学を講じ、幕政批判を行ったなどと、罪状を捏造(ねつぞう)して、同年5月崋山、長英ら一味を逮捕した。取調べの結果、無人島渡航計画などの容疑は晴れたが、幕政批判の罪は重く、同年12月、崋山には国元田原における蟄居(ちっきょ)、長英には永牢(えいろう)の判決が下された。これより先、小関三英は自分も罪の逃れがたきを思い自刃し、崋山、長英の両名もやがて自殺に追い込まれた。蛮学社中の観を呈した尚歯会そのものは、主宰者の紀州藩士遠藤勝助(しょうすけ)が逮捕されておらず、弾圧の直接対象にはなっていなかった。しかし、この事件は、蘭学・蘭学者が弾圧を受け、そこに幕府内における守旧派と開明派との対立が顕著にみられた事件であったといえよう。[片桐一男]
『佐藤昌介著『洋学史研究序説』(1964・岩波書店)』
◆鳥居耀蔵
とりいようぞう
(?―1874)
江戸時代、天保(てんぽう)の改革期の幕臣。名は忠耀(ただてる)。幕府儒官林衡(たいら)(述斎)の次男。2500石取の旗本鳥居一学の養子となる。幕府目付(めつけ)役となったのち、1841年(天保12)御勝手(おかって)取締掛を兼任、同年12月矢部駿河守定謙(するがのかみさだのり)のあと江戸南町奉行(みなみまちぶぎょう)に就任、甲斐(かい)守となる。水野忠邦(ただくに)の側近で、渋川六蔵(ろくぞう)、後藤三右衛門(さんえもん)とともに「水野の三羽烏(さんばがらす)」と称された。江戸庶民には「妖怪(ようかい)」(耀甲斐(ようかい))と恐れられるほどの強権政治を行ったが、目付として大塩平八郎の乱(1837)の事後処理にあたった経験がそうさせたともいわれる。39年江川英龍(ひでたつ)との対立、渡辺崋山(かざん)らを告発し処罰に追い込んだ「蛮社(ばんしゃ)の獄」や43年高島秋帆(しゅうはん)の下獄など開明派を弾圧し、内外の危機への回避策を幕府専権で守旧派の立場から推し進めようとした。上知(あげち)令では最後に反対派に回り水野と対立、失脚した水野の老中への再登場で罷免される。45年(弘化2)水野再辞任、その処罰の翌日、讃岐(さぬき)国(香川県)丸亀(まるがめ)藩主預けとなり、同年10月に禁固の処罰が下された。明治維新で放免。[浅見 隆]
『佐藤昌介著『洋学史研究序説』(1964・岩波書店) ▽北島正元著『水野忠邦』(1969・吉川弘文館)』
───────────────────────────
🔵渡辺華山の生涯
───────────────────────────

◆◆渡辺崋山の生涯(田原市博物館)
◆華山の生い立ち
渡辺崋山は、寛政5年(1793)9月16日、江戸麹町田原藩邸で、父定通29歳、母栄22才の長男として生まれました。当時、父は、留守居添役仮取次で15人扶持の給料をもらっていました。崋山は幼名を源之助より虎之助にかえ、8才で若君のお伽役となり、後に藩主より登の名を賜わりました。財政難の田原藩は家臣の減給を行っており、11名の家族で貧しい渡辺家は幼い弟妹たちを奉公に出さなければなりませんでした。このため崋山も貧しさを救うため、絵を描く内職をしながら学問に励みました。
◆藩士としての華山
写真/立志之像 天保3年(1832)崋山は家老に就任しました。そして、紀州藩破船流木掠取事件、幕命の新田干拓計画、助郷免除などの難かしい事件を解決しました。また、田原藩は救民のための義倉「報民倉」を建設し、天保7、8年の大飢饉では、一人の餓死流亡者も出しませんでした。このため、翌9年幕府は全国で唯一田原藩を表彰しました。これらは、崋山の指導による功績でした。この頃、黒船が近海に接近するため、崋山は外国船の旗印を描いて沿海の村々の庄屋に配り、海岸の防備や見張りに当たらせました。
◆学者としての華山
写真/報民倉 12才の崋山は、日本橋の暴辱から志を立て、徂徠学派の儒学者である鷹見星皐に学びます。後に佐藤一斎、松崎慊堂に学び、幕府の昌平黌にも学籍を置きました。また、当時の学者文人らと交友し、詩文、和歌、俳諧にも通じました。37才の時三宅氏の家譜編集を藩主より命ぜられ、続いて江戸では藩邸学問所の総世話役となり、儒者伊藤鳳山を招いて藩校成章館の興隆を計りました。晩年には貧しい中で集めた書籍などを、後輩のため藩へ献上しました。
◆画家としての華山
写真/渡辺崋山像 崋山は、白川芝山、金子金陵、谷文晁らに絵を学びました。初め、崋山の絵は家計を助けるものでした。しかし、天性の才能と努力によって26才頃には画家として有名になりました。崋山の絵には、鋭い線と品格があり、また、写生を主としていますが、外形だけでなく、内部の性格をあらわします。西洋画の立体、質、遠近などの面による構成を、線を主体とした東洋画に取り入れた功績は非常に大きく、その作品には、国宝「鷹見泉石像」をはじめ、多くの重要文化財、重要美術品が残っています。
◆外国事情の研究家
写真/池ノ原公園の渡辺崋山像
崋山は32才頃から外国事情に関心をもち、蘭学や兵学の研究を始めました。三宅友信に蘭学をすすめ、高野長英、小関三英、鈴木春山らを雇い翻訳をさせ、また鷹見泉石、幡崎鼎、江川坦庵ら洋学者とも交わり、来航したオランダ甲比丹から世界の状勢を知り、当時外国事情に精通する第一人者となりました。西洋諸国が強大な力をもって東洋に侵入するのに対し、幕府の外国船打払令や鎖国が危険なことを主張し、開国、交易をするよう強調しました。また、崋山の遺志は、藩士村上定平、萱生郁蔵らによって、明治維新まで受け継がれ、田原藩は軍備の近代化が最も進んだ藩となりました。
◆蛮社の獄
写真/自筆獄廷素描
蘭学の進出は儒学の信奉者が多い幕府役人にとって目の敵であり、目付鳥居耀蔵もその一人で、江戸湾測量で江川坦庵に敗れて以来、蘭学者の弾圧を狙っていました。幕府は、鳥居の密偵によって崋山らの無人島渡航計画の噂を知り、天保10年5月、崋山、高野長英ら10数名を捕らえました。渡航の罪は晴れたものの、崋山は机底から見つけられた「慎機論」、長英は「戊戌夢物語」が幕政批判という重罪となり、崋山は、在所田原へ蟄居、長英は永牢となりました。
◆華山の最期
蟄居中の崋山一家の生活を助けるため、門人福田半香らは崋山の絵を売る義会を始めました。崋山は作画に専念し、「于公高門図」「千山万水図」「月下鳴機図」「虫魚帖」「黄粱一炊図」など次々と名作を描きました。しかし、その活動により、天保12年(1841)夏の頃から「罪人身を慎まず」と悪評が起こり、藩主に災いの及ぶ事をおそれた崋山は死を決意しました。「不忠不孝渡邉登」と大書し、長男立へ「餓死るとも二君に仕ふべからず」と遺書して切腹し、49年の多彩な生涯を終えました。
写真/自筆遺書(渡辺立宛)
◆◆渡辺崋山
わたなべかざん
(1793―1841)
小学館百科全書
江戸末期の蘭学(らんがく)者、画家。諱(いみな)は定静(さだやす)、通称は登。字(あざな)は伯登または子安。華山のち崋山と号し、寓絵堂(ぐうかいどう)、全楽堂の堂号を用いた。三河国(愛知県)田原(たはら)藩士定通(さだみち)の長子として、江戸の藩邸内で生まれる。初め藩儒鷹見星皐(たかみせいこう)に儒学を学んだが、のち佐藤一斎(いっさい)に師事し、ついで松崎慊堂(こうどう)に学んだ。幼少から貧困に苦しみ、生計のために画を修業した。1824年(文政7)父の死によりその家督を継ぐ。32年(天保3)年寄役末席(家老)となり、藩務にあたり、殖産興業に努めるとともに、海防掛も担当した。このころ崋山は高野長英(ちょうえい)、小関三英(こせきさんえい)らの蘭学者と交わり、尚歯(しょうし)会を組織して西洋事情を研究し、古河(こが)藩家老鷹見泉石(たかみせんせき)をはじめ広く交際をもって、開明的政策を行った。37年、日本漂流民を伴い対日通商を目的として浦賀に来航したアメリカ船モリソン号が、異国船打払令によって撃退される事件(モリソン号事件)が起こり、これに対し、崋山は39年『慎機論(しんきろん)』を著し、長英らとともに、いたずらに世界情勢に目を覆い、人道に背く幕府の鎖国政策を批判した。このため同年5月蛮社の獄によって捕らえられ、12月、国元の田原に蟄居(ちっきょ)を命じられた。41年、崋山の窮迫を助けるため、弟子たちが江戸において開いた画会が、蟄居中不謹慎(ふきんしん)と誤り伝えられるに及び、崋山は藩主に累の及ぶのを恐れて自殺した。著作には、ほかに『鴃舌或問(げきぜつわくもん)』などがある。[片桐一男]
崋山は幼少より絵に親しみ、初め平山文鏡に手ほどきを受けたが、生計のためもあって本格的に画家を志し、16歳のとき白川芝山(しざん)につく。のち金子金陵(きんりょう)、ついで谷文晁(たにぶんちょう)に入門。初め沈南蘋(しんなんぴん)風の花鳥画を描いたが、26歳の作品『一掃百態(いっそうひゃくたい)図』では闊達(かったつ)な筆で庶民の日常のさまざまな姿態を生き生きと描き分け、独自の作風をみせている。一方、洋学への興味が西洋画への傾斜となり、29歳ごろより伝統的手法による衣服表現に加えて西洋画の遠近法や陰影をよく消化した立体感ある顔貌(がんぼう)表現で独自の肖像画を完成した。『鷹見(たかみ)泉石像』(国宝、東京国立博物館)、『市河米庵(いちかわべいあん)像』などのほか、その下絵にも傑作を残している。また写生帳『客坐掌記(かくざしょうき)』は、動きのある対象を的確に描写する筆致が生彩を放ち、本絵に欠落しがちな自由さと柔軟さにあふれている。ほかに『四州真景図巻(ししゅうしんけいずかん)』『千山万水(せんざんばんすい)図』『校書(こうしょ)図』『于公高門(うこうこうもん)図』『黄粱一炊(こうりょういっすい)図』などがあるが、崋山の画はいずれも武士としての生き方との相克のなかで、ときに自由に、ときに意志的にその描線の性格を変えつつ展開している。弟子に椿椿山(つばきちんざん)、岡本秋暉(しゅうき)がいる。[星野 鈴]
『森銑三著『渡辺崋山』(1961・東京創元社) ▽吉澤忠著『渡辺崋山』(1956・東京大学出版会) ▽鈴木清節編『崋山全集』(1910~15・崋山会) 『渡辺崋山』(1977・集英社) ▽蔵原惟人解説『渡辺崋山 一掃百態』(1969・岩崎美術社)』
◆慎機論
しんきろん
江戸後期の画家で思想家の渡辺崋山(かざん)が1838年(天保9)10月15日に高野長英(ちょうえい)らと参加した蘭学(らんがく)グループ尚歯会(しょうしかい)の席上で、近く漂流民を護送して再来日する「イギリス船モリソン号」(イギリス船というのは、オランダ商館が幕府に提出した風説書に基づく誤報で、事実としてはアメリカ商社の社船であった)に幕府はふたたび撃攘(げきじょう)策で対応するという噂(うわさ)を知り、これに反対して執筆した一文である。長英の『戊戌(ぼじゅつ)夢物語』(『夢物語』)と類同するが、打払令そのものに反対した長英とは異なり、頑迷な鎖国封建体制に対して、遠州大洋中に突き出した海浜小藩たる田原藩の藩政改革に関与する、現実的政治家崋山の批判を中心にしている。モリソン号に象徴される(『夢物語』と同様に、ここでも船名を人名と誤っている)イギリスの国情を詳述し、「今国家の拠(よ)る所海にあり」と「海船火技」の科学技術に注目した。ここから鎖国日本の現実を批判し、封建的太平の体制下にはびこる賄賂(わいろ)政治などを慨嘆した。「慎機」とは、かかる世界史の時勢にきざしたモリソン号来航に、為政者の慎重な対応を期すことであった。崋山は執筆を中断し秘して余人に見せなかったが、尚歯会への弾圧事件とされる蛮社の獄で、幕吏によって崋山宅から発見された。[藤原 暹]
『佐藤昌介校注「慎機論」(『日本思想大系55 渡辺崋山他』所収・1971・岩波書店)』
──────────────────────
🔵緒方洪庵の生涯と適塾
───────────────────────


◆◆紙芝居=緒方洪庵のたいまつ
【緒方洪庵おがたこうあん】
出典・紙芝居屋出前亭から
http://o-demae.net/library/literary01.html#up
司馬遼太郎原作 〔緒方洪庵生誕200年記念〕
唐突ですが、お釈迦様のニックネーム(別名・あだな)を知ってますか?
『大医王』なのですって。意味は〔偉大な医者の王様〕。そういえば、お釈迦様の教えに『応病与薬(おうびょうよやく)』というものがありました。その意味は「その人(病人=悩める人)に応じた、お薬(お話)を出して心と体を治す」ということらしいです。
確かに、お釈迦さまは、当時の超エリート王族のお一人だったので、医学知識は豊富だったでしょうが、それだけではなく、その人の心の苦しみの原因を見抜いて、治療されるのがお得意であったと思われます。今で言う『心理カウンセラー』であったのかもしれません。
さて、この日本にも、お釈迦さまのような《慈悲》のお心を持つ『大医王』がおられました。
しかも江戸時代後期に!その方は『宗教家』ではなく、本当のお医者さまでした。しかも、紛れもなく『お釈迦様』のようなお心を持たれた方。
「それは『JIN–仁』かって?」…あれは漫画のお話〔笑い〕。その方のお話を、今から紙芝居を使ってお話させて頂きましょう。そのお方の名は《緒方洪庵(おがたこうあん)》といいました。
世の為に尽した人の一生ほど、美しいものはありません。これから、特に美しい生涯を送った人についてお話します。
それは『緒方洪庵』という人の事です。
この人は、江戸時代末期に生れました。お医者さまでした。この人は名を求めず、利益を求めず、溢れるほどの実力がありながらも、他人の為に生き続けました。そういう生涯は、遥かな山河のように美しく思えるのです。
〔緒方洪庵〕は、今の岡山県〔足守〕という所で生れました。父は〔藩〕の仕事をする武士でした。
(洪庵)「父上、私は医者になりたいと思います!」
十二歳の時、突然〔洪庵〕は、父親に言いました。しかし、父は嫌な顔をしました。
(父)「武士の子は、どこまでも武士であるべきだ!!」
父は〔洪庵〕を立派な武士にしたかったのです。
では、なぜ〔洪庵〕は、それほどまで〔医者〕に成りたかったのでしょうか?
それは…
〔洪庵〕が子供の時、岡山の地で、《コレラ》という病気が凄まじい勢いで流行しました。人が嘘のように、ころころ死んだのです。〔洪庵〕を可愛がってくれた隣の家族も、たった四日間の間に、みんな死んでしまいました。
又、当時の《漢方医術》では、これを防ぐ事も治療する事も出来ませんでした。
(洪庵)「私は医者になって、是非人を救いたい。そして出来るなら、漢方ではなく、オランダの医術《蘭方》を学びたい!」〔洪庵〕は人の死を見ながら、こう決心したのでした。
しかし、〔洪庵〕の父の許しは遂に出ませんでした。そこで、〔洪庵〕は16歳の時、ついに置手紙をして家出したのでした。そして『大阪』へ向かいました。
なぜ、大阪だったかといいますと、その当時、この地で〔蘭方医〕が、塾を開いていたからなのでした。〔洪庵〕は、この塾に入門して、オランダ医学の〔初歩〕を学びました。又、幸いなことに、父親も大阪へ転勤となって移って来た為、やがて〔洪庵〕の医学修行も許してくれるようになったのでした。
大阪の塾で、すべてを学び取った〔洪庵〕は、さらに《師》を求めて江戸に行きました。そして、江戸では『あんま』をしながら学びました。
『あんま』をして、わずかなお金を貰ったり、他家の玄関番をしたりしました。
それは、今でいうアルバイトでした。
こうして〔洪庵〕は、江戸の塾で四年間学び、遂に〔オランダ語〕の難しい本まで読めるようになったのです。
その後、〔洪庵〕は『長崎』へ向かいます。長崎。当時、日本は鎖国をしていました。《鎖国》というのは、外国とは付き合わない、貿易しないという事です。
しかし、長崎の港、一ヶ所だけを、中国とオランダの国に限り、開いていました。長崎の町には、少しながら、オランダ人が住んでいました。
もう少し、《鎖国》についてお話します。
鎖国というのは、例えば、日本人全部が、真っ暗な箱にいると考えて下さい。長崎は、箱の中の日本としては、針で突いたような小さな穴で、その穴から、微かに《世界の光》が、差し込んでくる所だったのです。〔洪庵〕は、この長崎の町で、二年間勉強し、暗い箱の日本から、広く世界の文明を知ろうとしたのです。
29歳の時、〔緒方洪庵〕は大阪へ戻ります。そして、ここで『医院』を開いて、診療に努める一方、オランダ語を教え《塾》も開きました。
ほぼ同時に、結婚もしました。妻は〔八重(やえ)〕といい、優しく物静かな女性でした。〔八重〕は、終生〔洪庵〕を助け、塾の生徒たちから、母親のように慕われました。
〔洪庵〕は、自分の塾の名を、自分の号である〔適々斎〕から取って、《適塾(てきじゅく)》と名付けました。《適塾》は人気が出て、全国からたくさんの若者たちが集まって来ました。
《適塾》は、素晴らしい学校でした。
門も運動場もない、普通の二階建ての〔民家〕でしたが、どの若者も、勉強がしたくて、遠くからはるばるやって来るのです。
江戸時代は、身分差別の社会ですが、この学校はいっさい平等で、侍の子も、町医者の子も、農民の子も、入学試験無しで学べました。塾へは、多くの学生達が入学して来ましたが、先生は〔洪庵〕一人です。
〔洪庵〕は、病人たちの診療をしながら教えなければならないので、体が二つあっても足りませんでした。
それでも塾の教育は、うまくいきました。それは、塾生のうちで、よくできる者が、できない者を教えたからでした。
余談ながら、(わぁ~司馬遼調)僕は大学生の頃、三回ほどこの〔洪庵〕さんの作られた『適塾』に見学に行っている。今は中に入れるのかどうかは知らないが、昔(今から25年ほど前)は、見学できた。(僕の家からは自転車でも行けた)ほんとにこの狭い民家の中で、たくさんの学生達が、不眠不休で勉強していたのかと思うと、感動しまくりだった。(柱に刀傷もあったなぁ。ストレス溜まってたんやろなぁ・・)
僕は、村田蔵六(のちの大村益次郎)が、試験が終る度に、この『適塾』二階の物干し場に出て、豆腐をアテに酒を飲み、試験後の疲れを癒していたと小説『花神』で読み、実際、(オンボロになっていた)物干し場に出てみて、感動したのを覚えている。
この『適塾』、のちの『大阪大学 医学部』の卒業生で、この大学の教授になられた枚方市のホスピス医〔南吉一〕師と、のち御一緒に「紙芝居」を作る事になろうとは、その時、まだ知らなかった・・。(これも司馬遼調のパクリです)
〔洪庵〕は、自分が長崎や江戸で学んだ事を、より深く、熱心に教えました。〔洪庵〕は、常に学生たちに向かってこう言いました。
「君たちの中で、将来、医者に成る者も多くいるでしょう。しかし、医者という者は、とびきりの親切者以外は、成ってはいけない。病人を見れば、『可哀想でたまらない』という性分の者以外は、《医者》に成る資格は無いのです。
医者がこの世で生活しているのは、人の為であって、自分の為ではありません。決して、有名に成ろうと思わないように。又、お金儲けを考えないように。ただただ、自分を捨てて人を救う事だけを考えなさい。
又、オランダ語を勉強したからといって、医者にだけ成る必要はありません。自分の学んだ《学問》から、人を生かし、自分を生かす道を見つけなさい。」と…。
このような《教育方針》でありましたので、適塾からは、さまざまな分野の『達人』たちが生れました。幕末の戦争で、敵味方の区別なく傷を負った兵士を治療した『日本赤十字』の創始者や、又、今や壱万円冊の顔となった慶応義塾大学の創立者〔福沢諭吉〕など、多くの偉人たちを輩出しました。
やがて、そのような〔洪庵〕の評判を聞きつけた《江戸幕府》は、「是非、江戸に来て、『将軍』様専門の医者(奥医師)になってくれ」と言ってきます。それは、医者としては目もくらむような名誉な事でした。
しかし、〔洪庵〕は断りました。「決して、有名になろうと思うな。」という、自分の戒めに反する事だったからです。
しかし幕府は許さず、…ついに〔洪庵〕は「もはや断りきれない。討ち死にの覚悟で参ろう。」と、いやいや大阪を出発しました。
江戸に行った〔洪庵〕は、その次の年、そこであっけなく亡くなってしまいます。
もともと病弱であったのですが、江戸での華やかな生活は、〔洪庵〕には合わず、心の長閑さが失われてしまったのが原因でした。江戸城での、〔しきたり〕ばかりの生活に気を使いすぎ、それが彼の健康を蝕み、命を落とさせたのでした。
振り返ってみると、〔洪庵〕は、自分の恩師達から引き継いだ、《たいまつの火》を、より一層大きくした人だったのでしょう。
彼の偉大さは、自分の《火》を、弟子たち一人ひとりに移し続けた事でした。弟子たちの《たいまつの火》は、後にそれぞれの分野で、明々と輝きました。やがて、その火の群れは、日本の《近代》を照らす大きな明かりとなっていったのです。後生の私達は、〔洪庵〕に感謝しなければならないでしょう。
緒方洪庵、享年54歳。
おしまい。
◆◆WEB漫画=緒方洪庵
◆◆緒方洪庵
おがたこうあん
(1810―1863)
江戸末期の蘭方(らんぽう)医学者。文化(ぶんか)7年7月14日、備中(びっちゅう)国(岡山県)足守(あしもり)藩士佐伯瀬左衛門(さえきせざえもん)の三男として生まれる。幼名田上之助(せいのすけ)、名は章、字(あざな)は公裁、適々斎または華陰と号した。通称は三平、のち洪庵と改めた。1825年(文政8)父が大坂蔵屋敷留守居役になったため同行して大坂に出た。生来柔弱であり、武士に適さないと自覚し、病苦の人を救う医の道を志し、翌1826年中天游(なかてんゆう)の門に入った。4年後、苦心して江戸の坪井信道(しんどう)の塾に入り、3年間在塾。一方、宇田川榛斎(しんさい)、宇田川榕菴(ようあん)、箕作阮甫(みつくりげんぽ)らの指導も受け、学は大いに進んだ。そして洪庵の訳になる『人身窮理(きゅうり)小解』『視力乏弱病論』『和蘭詞解(オランダしかい)略説』『白内翳治(はくないえいち)術集編』などが写本で広く読まれた。また榛斎と榕菴の大著『遠西医方名物考 補遺』の度量衡表を分担執筆した。
1836年(天保7)長崎に赴く。オランダ商館長ニーマンJohannes Erdewin Niemann(1796―1850)について学んだともいわれるが、良友に恵まれ、青木周弼(しゅうひつ)、伊藤南洋(岡海蔵)(1799―1884)と『袖珍内外方叢(しゅうちんないげほうそう)』を共訳、好評を博し広く利用された。このころから洪庵を名のる。
1838年、中天游門下の億川百記の娘八重(1822―1886)と結婚、大坂・瓦(かわら)町に適々斎塾(適塾)を開き、1843年過書(かしょ)町(大阪市中央区北浜3―3)に移った。洪庵の名声は高く全国から俊秀が集まり、移転後の塾内寄宿門人は637名を数える(その名を記録した『姓名録 適々斎』は日本学士院に保存)。外塾生をあわせると2000人とも3000人ともいわれる。おもな塾生には、箕作秋坪(しゅうへい)、大鳥圭介(けいすけ)、佐野常民、長与専斎、柏原学而(かしわばらがくじ)(1835―1910)、福沢諭吉、花房義質(はなぶさよしもと)(1842―1917)、緒方郁蔵(いくぞう)、坪井信良(1825―1904)、石井信義(1840―1882)らがおり、また塾生の橋本左内(さない)は安政(あんせい)の大獄で、大村益次郎(ますじろう)は1869年(明治2)刺客に襲われたのちに死亡した。明治初期の政治家・軍人の列には薩長(さっちょう)の顔が、文化人の列には適塾の顔が並ぶ。
著書、訳書は多く、前出のもののほか、緒方郁蔵との共訳で全国に普及した大著『扶氏(ふし)経験遺訓』(30巻)や、安政のコレラ流行(1858)に際して出版した『虎狼痢治準(ころりちじゅん)』、『病学通論』(3巻)、ジェンナー牛痘種痘に関する写本『モスト牛痘説』などがある。
1849年(嘉永2)牛痘苗が輸入されて京都に到着した際、越前(えちぜん)藩医笠原白翁(かさはらはくおう)に分与を請い、厳かな分苗式を行った。そして大坂に除痘館(じょとうかん)を設け、大和屋(やまとや)喜兵衛、緒方郁蔵らの協力を得て種痘を行い、ついに奉行所(ぶぎょうしょ)から官許を得るなど天然痘の予防に貢献、その記録『除痘館記録』がある。
1862年(文久2)、洪庵は幕府の強い要請を受けて奥医師兼医学所頭取に就任した。しかし10か月後の文久(ぶんきゅう)3年6月10日、多量の血を吐いて急逝し、江戸駒込(こまごめ)高林寺と大坂の龍海寺に葬られた。贈従(じゅ)四位。現在、適塾は国の史跡・重要文化財に指定され、大阪大学が管理し一般に公開されている。[藤野恒三郎]
『緒方富雄著『緒方洪庵伝』(1942/増補版・1977・岩波書店)』
◆適々斎塾
てきてきさいじゅく
緒方洪庵(おがたこうあん)の蘭学(らんがく)塾。備中(びっちゅう)(岡山県)足守(あしもり)藩士の三男に生まれた緒方洪庵は、大坂の蘭医中天游(なかてんゆう)、江戸の坪井信道(しんどう)に学び、さらに長崎遊学後、1838年(天保9)大坂・瓦(かわら)町に開業し、蘭学も教え始めた。その学塾を適々斎塾(適塾)といい、1843年船場過書(せんばかしよ)町に移転後大いに発展し、全国から多数の門人が参集し、その数は3000人を超えたという。門人には、村田蔵六(大村益次郎(ますじろう))、武田斐三郎(あやさぶろう)、佐野栄寿(常民(つねたみ))、菊池(箕作(みつくり))秋坪(しゅうへい)、橋本左内(さない)、大鳥圭介(けいすけ)、長与専斎(ながよせんさい)、福沢諭吉、池田謙斎(けんさい)らがある。幕末期の塾の教育の実状は「元来適塾は医家の塾とはいえ、其(その)実蘭書解説の研究所にて、諸生には医師に限らず……凡(およ)そ当時蘭学を志す程の人は皆此(この)塾に入りて其仕度をなす」(長与専斎『松香私志』)というごとく、技術・知識の学としての蘭学を学ぶという傾向が強くなった。建物は国の重要文化財、また「緒方洪庵旧宅および塾」として国史跡指定を受け現存する(大阪市中央区北浜三丁目)。[沼田 哲]
『緒方富雄著『緒方洪庵伝』(1942・岩波書店) ▽緒方富雄編著『緒方洪庵適々斎塾姓名録』(1967・財団法人学校教育研究所) ▽沼田次郎著『洋学伝来の歴史』(1960・至文堂)』
──────────────────────────
🔵華岡青洲の生涯
──────────────────────────




はなおかせいしゅう
(1760―1835)
(小学館百科全書)
江戸末期の外科医。麻酔剤の開発を行い、麻酔下に日本最初の乳癌(にゅうがん)手術を行うなど積極的治療法を推進した。宝暦(ほうれき)10年10月23日、紀伊国(きいのくに)上那賀(なが)郡名手庄西野山村字平山(和歌山県紀の川市西野山)に生まれる。名は震、字(あざな)は伯行、随賢と号し、また居所の名をとって春林軒ともいう。父は村医者であった。23歳で京都に遊学、吉益南涯(よしますなんがい)(1750―1813)から古医方を、大和見立(やまとけんりゅう)(1750―1827)にオランダ、カスパル流外科を学び、在洛(ざいらく)3年ののち帰郷し家業を継いだ。古医方派の実証主義をとり、「内外合一、活動究理」、すなわち内科・外科を統一し、生き物の法則性を明らかにすることを信条として、積極的な診療技法を展開した。彼の開発した麻酔薬「通仙散」は、マンダラゲ(チョウセンアサガオ)を主剤とするもので、ヨーロッパの薬方に採用されていることを知ったのがヒントになり、中国医書を参考に改良を加えたものである。成分の配合と麻酔効果の関係を研究するため、たびたび被験者として協力した母は、おそらくその中毒によって死亡、妻も失明した。この麻酔薬を用いて多くの手術を行ったが、1804年(文化1)10月13日、紀州五條(ごじょう)の藍屋(あいや)利兵衛の母、勘に行われた乳癌摘出手術は日本最初である。手術は成功したが、患者は翌1805年2月に死亡している。このほかに乳癌手術だけでも150例ほど行っている。門人録に署名しているもの305人、広く全国から入門が相次いだ。天保(てんぽう)6年10月2日死去。[中川米造]
『呉秀三著『華岡青洲先生及其外科』(1923・吐鳳堂書店/複製・1994・大空社) ▽松木明知著『華岡青洲と麻沸散――麻沸散をめぐる謎』(2006/改訂版・2008・真興交易医書出版部)』
◆◆WEB漫画=華岡青洲
◆◆杉田玄白の青洲宛の書簡
杉田玄白が華岡青洲の業績を知り、華岡青洲に送った手紙。
未だ貴意を得ず候へども一書呈上致し候。時分柄薄暑と相成り候へども弥々御安清にならせられ候由、目出たく存じ奉り候。
然れば老兄の御高名は江戸表まで相聞え御頼もしく存じ罷り在り候。旧年以来かねて御随身中に罷り在り候由の宮川順達と申す加賀の書生出府致し委しき御噂承知致し候。数年御治療のところ被労御精心の段ほぼ承りさてさて御頼もしく存じ奉り候。
老拙儀も二三世外治を以て旦那家に仕へ罷り在り候こと故何卒生民の為め少しにても治業の慮らひ工夫致し候て益にも相成りたく年来心懸け候へども差したる義もこれなく、犬馬の老積り最早当年八旬に及び空しく朽ち果て申すべく残念に存じ奉り候。
さりながら老驥伏櫪の志は相止み申さず折節不審の義有之候へども本科は格別同業の者には海内に承り及び候者もこれなく候。幸ひ老兄の御噂承り及び候へどもこれまで好縁も御座なく罷り在り候。順達罷り越し候て御手術御煉熟の段申し聞けさてさてと感心致し候ことに御座候。
江戸表は御聞及びもこれあり候哉。手を下し候はば宜しかるべしと存じ候病人も間々これあり候へども比々白面貴价の公子のみにて痛苦を忍び候ものこれ無く拙業とは存じながらその術施し難く打過ぎ候ことばかり多くこれあり候て遺憾少なからず候。 さりながら以来不審の義もこれ有り候はば御文通にてなりとも御相談申したく候。拙者は老衰に及び候へども倅どもの為めにも御座候間彼等より申し上げ候ことも御座あるべ候。御許容なし置かれ下さるべく候。
順達より書面差上げ候様承り候間卒忽ながら申し上げ候。以来御知己の内へ加へられ置き下さるべく頼み奉り候。恐惶謹言。
五月四日 杉田玄白 翼花押
華岡随賢様人々御中
参考文献 上山英明「華岡青洲先生その業績とひととなり」医聖・華岡青洲顕彰会
憲法とたたかいのブログトップhttps://blog456142164.wordpress.com/2018/11/29/憲法とたたかいのblogトップ/